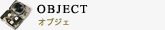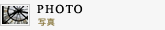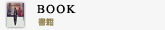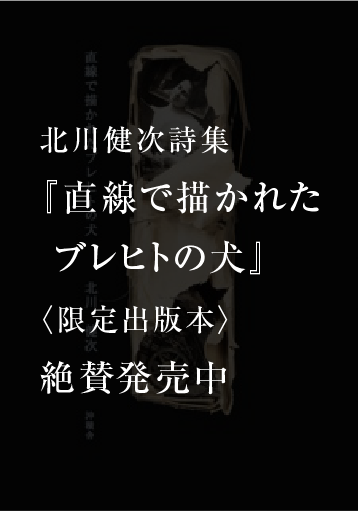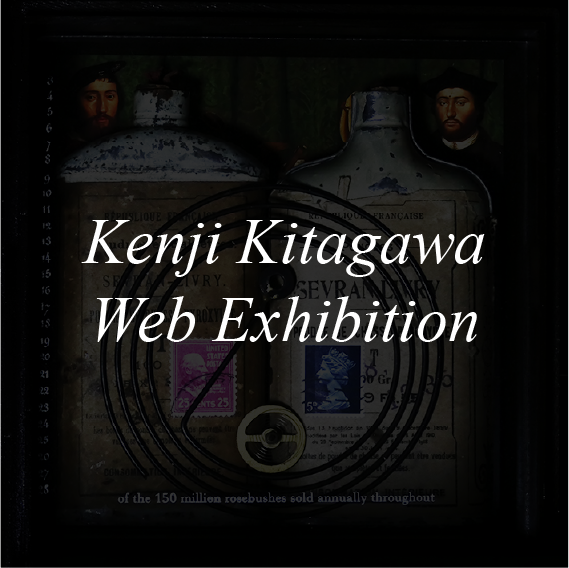…昨年の夏よりも更に酷暑となった今夏の異常さはもはや尋常ではない。…北海道が40度に迫り、熱中症の患者も今年は実に多いという。…多いと云えば熊の被害も増えている。…テレビで、人家の庭から悠然と去っていく熊の後ろ姿を観たが、あたかも親戚の叔父さんが東京土産に亀屋万年堂のナボナを置いて帰っていくような……、そんな感じである。
……先日、東京恵比寿のLIBRAIRIE6で開催していた個展が盛況の内に終了した。…来廊された方がSNSで今回の個展情報を発信する回数が多いらしく、画廊に来廊者がいなかった時がない。…初めて私の作品を知った方もいて、美術に対する認識が広がったのか、長時間観入っている方がかなりいた。
…さて、一転して昭和の話を。……ずっと以前から気になっている事があった。…それは私が中学の時に福井から東京に修学旅行で来た時に泊まった旅館の事である。(それは日本学生会館という名前で、神田川沿いの中央線・御茶ノ水駅と水道橋駅の間の坂道に在った)……生来不穏な怪しい気配に惹かれている私は、その旅館(と言っても、重厚な鉄筋コンクリートの建物)が放っている、何とも事件の匂いがするその入り組んだ造りや、隠し部屋さえありそうな、…そんな二重構造めいた気配の事が記憶に長く残っていた。…そしてひと頃、美術家と併せて私立探偵業をやろうと本気で考えていて、事務所の物件を探していた時に、イメ-ジの範として、その建物の事が頭にあった。
 先日、古書店で川本三郎さんの『名作写真と歩く昭和の東京』という本を買ったら、その中に、その建物の来歴が載っていて驚いた。その本の中に一枚の写真が載っていた。陽炎の中に電車や車が浮かび上がったような幻想的な写真。…写真家・植田正治の初期の写真である。…川本三郎さんの説明によると、坂の左手の暗い固まりに、順天堂医院、昭和第一工芸高校、…そしてモダンな鉄筋コンクリートの建物…お茶の水文化アパ-トがあった。…文化アパ-トは大正14年にアメリカの建築家ヴォ-リズの設計によって作られた高級アパ-ト。…それが戦後、進駐軍将校の家族宿舎になった後に旺文社が買い取り、修学旅行生の宿、日本学生会館となったが、老朽化のため取り壊されたとあった。
先日、古書店で川本三郎さんの『名作写真と歩く昭和の東京』という本を買ったら、その中に、その建物の来歴が載っていて驚いた。その本の中に一枚の写真が載っていた。陽炎の中に電車や車が浮かび上がったような幻想的な写真。…写真家・植田正治の初期の写真である。…川本三郎さんの説明によると、坂の左手の暗い固まりに、順天堂医院、昭和第一工芸高校、…そしてモダンな鉄筋コンクリートの建物…お茶の水文化アパ-トがあった。…文化アパ-トは大正14年にアメリカの建築家ヴォ-リズの設計によって作られた高級アパ-ト。…それが戦後、進駐軍将校の家族宿舎になった後に旺文社が買い取り、修学旅行生の宿、日本学生会館となったが、老朽化のため取り壊されたとあった。
面白かったのは、その後の記述である。…このモダンな鉄筋コンクリートの建物、お茶の水文化アパ-ト(後の日本学生会館)は、江戸川乱歩が創造した名探偵、明智小五郎が昭和四年頃に住んでいた「開化アパ-ト」のモデルとされている。…という記述を読んだ時に、その建物への私の拘りが氷解したのであった。…私と同じく江戸川乱歩もまたあの建物に、不穏で怪しい気配を覚えていた事を知ったのであった。…そればかりか、島田荘司のミステリ-小説『網走発遥かなり』にも、乱歩ファンの女性が、まさに取り壊し中のこの建物を見るくだりがある事も知ったのであった。
…先日、箱根にある「箱根写真美術館」(館長は写真家の遠藤桂さん)から展覧会の美しいご案内状が届いた。…写真家・榎村綾子さんの個展『仮説から始まるロマネスクの幻視』である。…今年の1月に遠藤桂さんと日本記者クラブのカフェでお茶をした時に、榎村さんの個展を夏に開催するお話しは伺っていたが、それがいよいよ実現したのであった。…榎村さんの写真は、パリやロンドンなどに流れる硬質な時間や歴史の層に被写体を求め、巧みな表現力を駆使して、現実と幻のあわいに立ち上がる詩情を浮かび上がらせるという、写真の分野でも他に類が無い表現で知られる特異な存在である。……この国を代表する国際的な写真家で知られる川田喜久治さんは、榎村さんの写真集にテクストを書いて高く評価しているが、その写真を観た確かなプロの眼を持った遠藤さんが独自に評価して、今回の個展となったのであった。…………
遠藤さんとの出会いは、今から15年以上前になるであろうか。…銀座を歩いていた時に、ある画廊で開催されていた写真の個展を通りがかりに観た時に、一瞬でその写真から放たれている強い「気」を受けて、私は画廊の中に入った。…写真はパリの主に風景を撮した作品であったが、昨今ますます衰弱している写真の分野にあって、そこに展示されていた写真の数々からは、真逆ともいえる、パリの建物などの被写体を通した奥にある、何か言葉では名状し難い「光の魔力」といったものの潜みが感じられたのであった。…(私はあなたの作品、好きですよ!実にいいですね!!)…確かこのような言葉を、画廊にいた作者に話したのだと記憶している。…作者のその人は、その瞬間に実にいい笑顔を私に返してくれたのであった。…それが写真家・遠藤桂さんとの出逢いであり、以来親交が続いている。
…遠藤さんは海外からの仕事も含めて写真の様々な仕事をこなしておられるが、その中心には霊峰とよばれる富士山が存在し、その霊的ともいえる富士山の様々な相貌を捕らえる事を生涯の主題としている人である。…ここに遠藤さんの作品を一点、ご紹介しよう。タイトルは『楓月-KAZUKI』。昨年の12月にパリの個展で発表した作品である。

……(北川さん、箱根は別天地のように涼しいですよ。)…私のオブジェを数多くコレクションし、また広重の版画のコレクタ-としても知られるTさんは、箱根に別荘を持っていて夏は避暑で箱根に住んでおられるが、先日頂いたメールには、そう書いてあった。新幹線こだまで、新横浜から小田原駅までは僅かに15分で着き、箱根登山鉄道で強羅駅で降りると箱根写真美術館はすぐであった。…楕円形の会場には榎村さんの写真作品がおよそ30点近く展示されていて、各々の作品から放たれている独自な気配が壮大な幻想の交響を産んでいて、素晴らしい個展だと実感する。
…何れも作品の完成度が高く、美的なものへの共振力が強い美学の谷川渥さんが、写真家の川田喜久治さんとはまた別な切り口で、テクストを執筆している理由も頷ける。…ここに榎村さんの写真作品を4点、ご紹介しよう。4点何れも表現の攻めるメソッドを変えながらも、しかし何れも美と毒と、深い詩情が作品の表象を領し、古典が放つ韻が今日性と絡み合って、強い引力を孕んだ表現世界を立ち上げているようである。
…………ここ箱根写真美術館は、猛暑とは無縁の、涼風が吹き抜けていく別天地のような美術館であった。遠藤さんご夫婦とも併設してあるカフェで久しぶりに愉しい時間を過ごす事が出来て日々の疲れが一掃され、充電も出来た。……会期は9月8日までだが、制作の合間を見つけて今一度訪れようと、私は思った。



榎村綾子写真展『仮説から始まるロマネスクの幻視』

2025年7月23日(水)~9月8日(月)。
AM10時~PM17時30分
〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-432
TEL.0460-82-2717
小田原駅から箱根登山鉄道「強羅駅」下車・徒歩5分。「公園下駅」から下車してすぐ。カフェ併設。(休館は火曜・第3月曜)

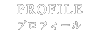
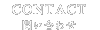










 …用事を済ませてアトリエに戻ったら、郵便受けに大きな封筒が。…差出人を見ると
…用事を済ませてアトリエに戻ったら、郵便受けに大きな封筒が。…差出人を見ると その四方田さんの著書『人形を畏れる』の冒頭は、私が持っていた不気味で土着的な人形に対する記述から始まり、次に私が登場する。
その四方田さんの著書『人形を畏れる』の冒頭は、私が持っていた不気味で土着的な人形に対する記述から始まり、次に私が登場する。
 森さんが生前にお付き合いした人達の事を綴った点鬼簿のような本である。…私も生前に親しくして頂いた名書評家で作家の
森さんが生前にお付き合いした人達の事を綴った点鬼簿のような本である。…私も生前に親しくして頂いた名書評家で作家の
 …
…

 先日の5日、銀座の
先日の5日、銀座の
 …私は観ている途中でふと、彼の見事な身体表現に最も相応しい観客は誰か…と考え、すぐに
…私は観ている途中でふと、彼の見事な身体表現に最も相応しい観客は誰か…と考え、すぐに




-828x1024.jpg)









 …前述した山口さんとの出逢いは私の詩集であったが、執行さんとの出逢いもまた一冊の本からであった。…NHKエデュケ-ショナルの方が拙著
…前述した山口さんとの出逢いは私の詩集であったが、執行さんとの出逢いもまた一冊の本からであった。…NHKエデュケ-ショナルの方が拙著
 昨日の9日(個展初日)の昼過ぎに、金沢の画廊
昨日の9日(個展初日)の昼過ぎに、金沢の画廊 ……私はホテルに一泊した後、翌日は短い時間であるが、風情ある浅野川河畔に焦点を絞って歩いた。先ずは
……私はホテルに一泊した後、翌日は短い時間であるが、風情ある浅野川河畔に焦点を絞って歩いた。先ずは …種村さんが亡くなられてから久しいが、久しぶりに再会した気分がして懐かしかった。他に、
…種村さんが亡くなられてから久しいが、久しぶりに再会した気分がして懐かしかった。他に、