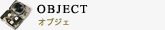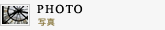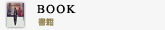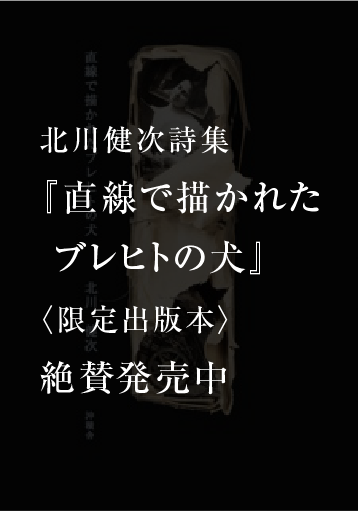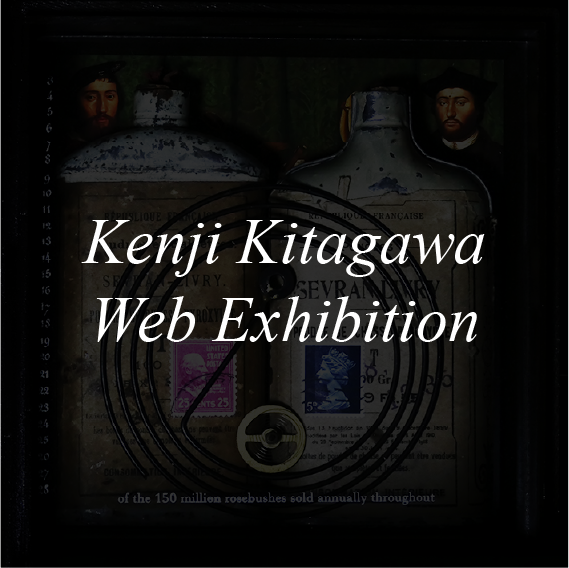年末にアトリエの片付けをしていたら、ガサリと1冊の本が棚から突然落ちて来た。…!?と思って手に取ると『乱歩-キネマ浅草コスモス座』(高橋康雄著)という本であった。(乱歩とは江戸川乱歩の事である。)開いて読み始めたら気になる章があったので、掃除はさておき読み耽ってしまった。その気になる章のタイトルは「もくづ塚」。
年末にアトリエの片付けをしていたら、ガサリと1冊の本が棚から突然落ちて来た。…!?と思って手に取ると『乱歩-キネマ浅草コスモス座』(高橋康雄著)という本であった。(乱歩とは江戸川乱歩の事である。)開いて読み始めたら気になる章があったので、掃除はさておき読み耽ってしまった。その気になる章のタイトルは「もくづ塚」。
書き出しはこうである。………(昭和9年の春、乱歩は久しぶりに浅草に出向いた。(略)…土地の人らしい年配の男に出会ったので乱歩は道を訊いた。「慶養寺に行きたいんですが…」。
……この冒頭から私は忽ち掴まれてしまった。…年末のブログに登場した二人の人物。版画家小野忠重と、彼の家に入ったまま、以後その姿を現す事なく、この世から24才の若さで消えた(或いは消されてしまった)、才能ある版画家藤牧義夫の両名とその事件。…その限りなく黒と目されている小野忠重の墓が在るのが、乱歩が行こうとしているこの慶養寺なのである。

乱歩が寺に現れたのが昭和9年。この同年に藤牧は全4卷・全長60mに及ぶ大作『隅田川両岸絵巻』などを完成させ、小野が率いる「新版画集団」の中でも抜きん出た才能を発揮するという新境地を見せていた。正にこれから飛躍の勢いである。
しかし、翌、昭和10年9月2日の夜、藤牧は姉の太田みさお宅から、もう一人の姉の嫁ぎ先の中村てい宅に行く途中で、その中間の場所にある小野忠重宅に行き、家に入ったまま永遠に出る事なく、僅か24才という若さで、以後終に現れる事はなかった。
…姉の中村ていは、待っていた弟の藤牧が来ないので、騒ぎだして事件が明るみとなる。…小野は、さも藤牧が憔悴、絶望のあまり、涙ながらに小野の家を出てその足で隅田川に入水したかのような、リアリティも根拠すらない放言に終始し、新版画集団の連中も、主宰する小野への忖度と、才能ある藤牧への嫉妬も絡んでか、懸命な捜索もされないまま、この集団は解散する。
…さて、藤牧が消えて、それから僅か7ケ月後の昭和11年の3月に、小野は急に不審とも思える行動をとった。その時未だ26才であるというのに、…この慶養寺に小野は自分の墓を作ったのである。…そして藤牧はといえば、未だその死体はいっこうに発見されていないままである。昭和11年3月と云えば、その前の2月に2.26事件、そして5月には阿部定事件…と、時代は血生臭い不穏な気配を帯び始めた頃である。…そんな時に小野は、まるで何かに急かれるように、なぜ墓を作るなどという行為に突然意識が向かったのであろうか。……
…………江戸川乱歩が、この慶養寺に来た目的は、この寺に在るという「もくづ塚」という塚を見る為であった。本を読んでいくと興味ある記述が次々と拡がっていく。その文を少し拾おう。
(…乱歩が今、慶養寺を訪れたのは、最後の「藻屑物語」の采女、右京の二少年の悲恋物語への関心に端を発していた。徳川初期に起こった武士道的少年愛の事実を美しく綴ったものである。仮名草子の稚児(ちご)物語の作風と西鶴武道ものの作風との、ちょうど過度期に属するものである。…(略)…「実は『藻屑物語』の采女右京の墓があるのではないかと…」と乱歩は口ごもりながら聞いた。住職も珍しいこともあるものだといわんばかりに乱歩の顔をまじまじと見つめた。そんな珍客は初めてのことであった。「もくづ塚ならあります」住職は言った。(略)…雑草におおわれて、無残な姿であった。
………この文を読んでわかるように、もくづ塚のある慶養寺は、男色者における聖地のようなものでもあり、当時、古ギリシャや日本の古代からの同性愛文献資料あさりをしていた乱歩は、その収集目的で、この寺を訪れたのであった。

………読者の方は覚えておられるであろうか。
…年末のブログに掲載した、新版画集団の展覧会の集合写真で、小野が藤牧の肩に手を回し、あたかも好色な僧が、年少のまだ少年の面影すらある藤牧義夫を、自分の可愛い稚児の様にして写っている、一見して異様な1枚の写真の事を。
…そして検証の意味で、私の友人の画家で男色者のM氏に見せたところ速断で、この写真から直に自分達の側にいる人間特有の気配が伝わってくると証言した事を。
…アトリエの片付けをしている時に、まるで推理の促しのように棚から落ちて来た、乱歩について書かれた1冊の本。…読んでいて知った事実。…乱歩はこの後も数回、この慶養寺を訪れているのであるが、…すると、後にこの「もくづ塚」の事を随筆で書く為に寺を訪れている乱歩と、その後ろにある墓地に墓を作っている最中の小野忠重が同時期にいた可能性が見えてくる。
1月16日、私は、この事件に強い関心と推理を寄せているブックデザイナ-の長井究衛君と一緒に、浅草今戸にある慶養寺に行くべく予定を立てていた。その前夜にM氏(画家にして男色者)に、もしやの誘いのメールを入れると(私も行きます。小野の墓には興味がありますので)という返事。…いつもなら私単独で現場に行くのが常であるが、友人を誘ったのは他でもない、…なかなか見つからないという『もくづ塚』を、複数なら探しやすいという事と、藤牧が消えたほぼ直後と言っていい数ヵ月後で、何かを急ぐかのように僅か26才で墓を作った小野の深意解析について、長井君、M氏各々のご意見にも興味があったからである。

11時に待ち合わせして浅草の老舗の神谷バ-で昼食をとり、タクシ-で慶養寺へと向かった。(因みに私が寺に来るのは2回目である)。住職に来意を告げて、先ずはもくづ塚を探した。…気のせいか、歩く乱歩の影が木々の間や葉群らの影に幻のように過って見える。しかし…件の塚はなかなか見つからない。…彼ら二人は寺の奥に更に探索を拡げ、私は住職に寺の歴史を問うた。…住職は奥から江戸時代に画かれた絵地図を探して来て見せてくれた。…建物に道を塞がれている今と違い桁違いの巨大な寺院で、すぐ目の前が隅田川である。

…私は了解した。…乱歩や小野・藤牧の頃(昭和10年前後)は未だ寺は広大な敷地を有していたが、空襲、そして戦後の荒廃で、寺の敷地を貸したり、売却するなどして、その時に件の「もくづ塚」も破壊されてしまったのだと。…今の住職がもくづ塚の在所を知らないという事が、その証であろう。
…さて、次は小野の墓である。…この古刹慶養寺にはそれなりの墓地があって墓もあるが、歴史が古いので、何れの墓も朽ちたようにかなり古い。…そんな中で、小野の墓は薄いピンク色をした石で目立って新しく、裏側に「昭和11年3月再建 小野忠重」とだけ彫ってあり、普通なら刻してある筈の親や先祖の各人の享年月日が、この墓にだけは一切無いのが異様であった。……「再建」の文字の意味を住職に訊くと、この小野の墓の場所は江戸時代から小野の先祖が所有していたが、縁者の骨は再建の際に何らかの意図で一掃されてしまった可能性もあるという。…理由まではさすがに寺もわからないと言う。

…その日は暖かく汗ばむ陽気であったが、墓の前に立っていると、妙に重い冷気が時おり肌を撫でていく。…墓地全体に目をやると、何れの墓も肉親や縁者が立てた、死者を供養する卒塔婆が何本も立っているが、…ただ小野忠重の墓には一本も無く、花を供える花立てに花筒もなく、枯れた花すらも無いのが、無常の冬ざれとして映った。
……私達三人は墓の前で無言であった。………しかしこの墓には、小野以外に何かが、…いや誰かの存在した証しとおぼしき魂の一片が、今も確かにこの墓の暗いくぐもりの中にさ迷っているような、そんな気配をふと覚えたのであった。闇の中のもう一つの闇に。そして私は思った。………他でもない、もう一つの「もくづ塚」はここに在ったのだと。
…お詫び。ブログが本件で終始してしまいました。予定にあったダ・ヴィンチのモナ・リザ、次回に渾身の気持ちを入れて書きます。

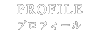
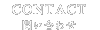





 …わが国の幻想文学の頂点に立つと言っていい江戸川乱歩の名作『押絵と旅する男』は、
…わが国の幻想文学の頂点に立つと言っていい江戸川乱歩の名作『押絵と旅する男』は、 ……浅草十二階をネットで開けば、私のブログが出てくるし、1994年6月号に刊行された『太陽』の江戸川乱歩特集・「怪人乱歩・二十の仮面」では、私は『蜃気楼』と題して、浅草十二階への想いを熱く語っているのである。
……浅草十二階をネットで開けば、私のブログが出てくるし、1994年6月号に刊行された『太陽』の江戸川乱歩特集・「怪人乱歩・二十の仮面」では、私は『蜃気楼』と題して、浅草十二階への想いを熱く語っているのである。




 …端整であった藤牧の顔つきが昭和8年から、消えた昭和10年の2年間に一変しているのである。…これは忽ち、新版画集団の中でも突出して才能を開花させて來た藤牧の自信の現れだと思うが、…それにしても初期の、姉と撮した顔の、あたかも歌舞伎役者の女形(おやま)を連想させるような優男顔……。そしてこの世から消えてしまう年に撮された顔は、男として芯のある顔へと変貌している。
…端整であった藤牧の顔つきが昭和8年から、消えた昭和10年の2年間に一変しているのである。…これは忽ち、新版画集団の中でも突出して才能を開花させて來た藤牧の自信の現れだと思うが、…それにしても初期の、姉と撮した顔の、あたかも歌舞伎役者の女形(おやま)を連想させるような優男顔……。そしてこの世から消えてしまう年に撮された顔は、男として芯のある顔へと変貌している。

 1つは
1つは ……もう1つは谷中の
……もう1つは谷中の
 …当日は彼の代表作の一つである
…当日は彼の代表作の一つである






 ……また夢は時に、脳の潜在的な能力の深淵を垣間見せてくれるような、唯、不思議としか言い様がない事も見せてくれる。
……また夢は時に、脳の潜在的な能力の深淵を垣間見せてくれるような、唯、不思議としか言い様がない事も見せてくれる。 …その夢は明るい光を放ち、その光の真ん中に、私が昨日まで取り組んでいたオブジェがあり、…驚いた事に、作品は完成した姿となってそこに在るのであった。(……何だ‼出来ているじゃないか‼)…夢の中で私はそう声高に叫んだ。
…その夢は明るい光を放ち、その光の真ん中に、私が昨日まで取り組んでいたオブジェがあり、…驚いた事に、作品は完成した姿となってそこに在るのであった。(……何だ‼出来ているじゃないか‼)…夢の中で私はそう声高に叫んだ。
 ………これは夢の別な話であるが、夢の中で全く自分の知らない人達が現れて来て、私の方に実に親しげな笑顔を見せる。…すると私はえも言われぬ懐かしさがこみ上げて来て、彼らに対して微笑を返す。
………これは夢の別な話であるが、夢の中で全く自分の知らない人達が現れて来て、私の方に実に親しげな笑顔を見せる。…すると私はえも言われぬ懐かしさがこみ上げて来て、彼らに対して微笑を返す。

-695x1024.jpg)