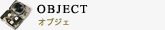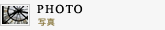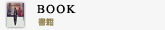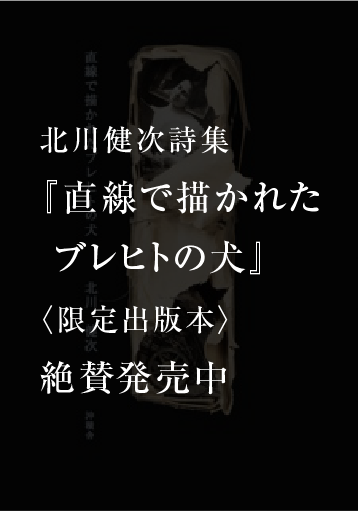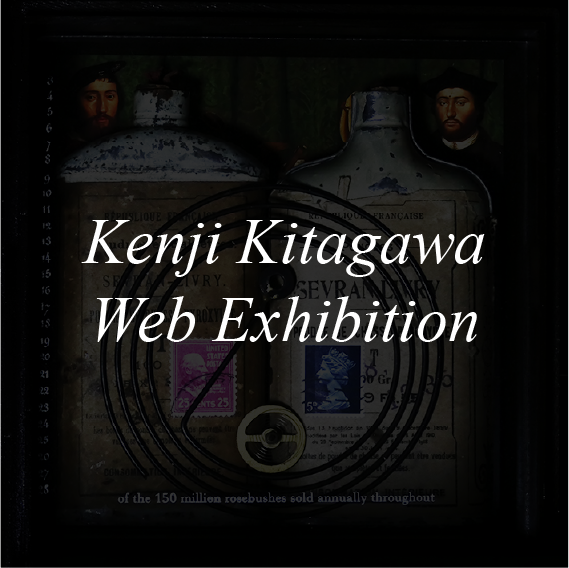…一度しかない人生を豊かにするか否かは、善き人との出逢いが大きい。…その意味では私は本当に善き人達との出逢いに恵まれていると思う。…わけても先達の人で、今も現役の活動をされている人達からは知的刺激と強い気を頂いている。…5月に名古屋画廊で私との二人展を開催した俳人で美術評論家の馬場駿吉さん(93才)、海外でも最も高い評価のある写真家の川田喜久治さん(92才)、…そしてアンドレ・マルロ-と親しく、『マルロ-との対話』他の著作でも知られる仏文学者の竹本忠雄さん(93才)。…竹本さんは八月に刊行予定の新フランス詩華集『幽憶』のランボ-の『太陽と肉体』の訳に併せて、私の版画『肖像考-Face of Rimbaud』(戸嶋靖昌記念館収蔵)が掲載される予定。刊行が楽しみである。……そして、わが国のシュリアリスム研究の第一人者で瀧口修造さんやアンリ・ミショ-とも親交が深かった鶴岡善久さん(89才)……etc。
その鶴岡さんを先日、船橋に訪うた。鶴岡さんの部屋はいまだに書籍の山で、壁には、私の個展の案内状が沢山貼られていて感動した。…その日は二時間ばかりの滞在であったが、国家とは、そしてそもそも天皇性とは何なのか、…その是非について、また川端、三島、谷崎、大江健三郎、梶井基次郎…の話に移り、最後は、この国の本来は在るべき軌道であったものを狂わせてしまった西郷隆盛の農本主義と大久保利通の富国強兵をスローガンとする、ドイツを規範とした政策の対立について意見を交換して、時間があっという間に過ぎてしまった。……大久保利通…欧化主義…、そして紀尾井坂の大久保が暗殺された現場の事が帰路の際に頭に残ったのであった。

周知のように、征韓論で敗れた西郷隆盛は鹿児島に下野し、明治10年2月から9月迄続いた西南の役で、故郷の城山で自刃して果てた。ここに於いて農本主義の可能性は無くなり、以後は大久保利通が牽引する富国強兵策によって、日本は本来の気質や精神の身の丈に合わない路線を狂歩する事となった。
…だが、その大久保は8ヶ月後に、政府の専制的な政治や富国強兵策などの不満を抱いた島田一郎ら6名の不平士族によって紀尾井坂の清水谷付近で暗殺された。…いわゆる『紀尾井坂の変』である。
 ………その暗殺現場のあった場所(ホテルニューオ-タニ前近く)を私は度々通っている。拙著『美の侵犯』や作品集『危うさの角度』刊行の為に出版社・求龍堂に打ち合わせに行く時に、私は好んでその道を通っていたのである。
………その暗殺現場のあった場所(ホテルニューオ-タニ前近く)を私は度々通っている。拙著『美の侵犯』や作品集『危うさの角度』刊行の為に出版社・求龍堂に打ち合わせに行く時に、私は好んでその道を通っていたのである。
…ある時から関心は、大久保を斬殺した島田一郎ら6名にも及び、谷中墓地に在るという彼らの墓を見に行った事があった。…しかし一万基は在るという広大な墓地で捜すのは不可能に近い。…だが、私には呼び寄せる力があるらしく、その時も私に吸い寄せられるようにして、墓地内で墓を案内する年輩の男性が何処からか不意に現れた。

…(大久保を斬殺した島田一郎達の墓を見に来たのですが、わかりますか?)と言うと(あぁ、わかるよ!付いてきな!)と言って歩き出した。案内のその男は急に振り向いてこう言った。(俺も30年以上、この墓地の案内をしているが、島田一郎達の墓を尋ねて来たのは、あんたが初めてだよ)と。
…そして前を歩きながら男は独り言のようにこう言った。(…あの島田一郎は確か鳥取藩だったな)と。…私は言った。(いえ、島田一郎は石川県士族です‼)と。………男は急に振り向いて、伝法な物言いでこう言った。(あれかぇ?お前さん…ひょっとして訳ありの人かい?)と。…(いえ、私は只の人間です。)
……かくして私は案内されて、その刺客6名の墓の前に立った。…そこは横山大観の墓裏の昼なお暗い場所であった。
 …よほど私は不穏な凶事の気配が好きなのであろうか、…現場主義の私は大久保が災難時に乗っていた、血痕が生々しく残っている馬車を皇居三の丸尚蔵館で展示された時にも観に行っている。
…よほど私は不穏な凶事の気配が好きなのであろうか、…現場主義の私は大久保が災難時に乗っていた、血痕が生々しく残っている馬車を皇居三の丸尚蔵館で展示された時にも観に行っている。
そして先日、……梅雨入りの冷たい雨がしめやかに降る午前に、桜田門にある警視庁参考室に行き、暗殺時に島田一郎らが使った刀が展示されているので、事前予約を入れてそれを観に行った。
 ……大久保利通の乗った馬車が近づいて来た瞬間、刺客は先ずは馬の脚を斬り、次に馬丁を斬った後に、大久保を馬車から引きずり出して16ケ所を斬って斬殺した。
……大久保利通の乗った馬車が近づいて来た瞬間、刺客は先ずは馬の脚を斬り、次に馬丁を斬った後に、大久保を馬車から引きずり出して16ケ所を斬って斬殺した。

… (⭕注意・ここから以下は血圧の低い人や、10才未満のお子様は読まないようにお願いします。全て実際にあった話です。) ↓
大久保は暗殺される前日に前島密(郵便制度の父・当時内務省の官僚であった)にこう言ったという。…(昨夜、不思議な夢を視たよ。西郷と私が高い岩山の上で縺れ合いのように取っ組み合いをしながら、やがて二人とも下に堕ちてしまうのだが、自分の頭が割れて、脳みそがピクピクと動いているのを、もう一人の自分がじっと視ている、そんな夢を視たよ。)と。
明治11年5月14日、午前9時頃、内務卿大久保利通が刺客に襲われた‼という一報が赤坂仮御所に入った時に、真っ先に現場に駆けつけたのは前島密であった。…そして前島はそこで視たのであった。…大久保が前日に語った通り、柘榴のように切り裂かれた大久保の割れた頭蓋骨の中で、未だその脳みそがピクピクと動いている、その光景を。………私は警視庁のその展示室に在った刺客が使った刀の切っ先が4センチばかり欠損しているのを視た時に、大久保の頭蓋をも切り裂いた、日本刀の物凄い力を想像し、その大久保が語った予知夢のような不思議な話を思い出して戦慄した。
 しかし、この予知夢のような話を分析すると、2つばかり、大久保の深層心理らしきものが見えてくる。
しかし、この予知夢のような話を分析すると、2つばかり、大久保の深層心理らしきものが見えてくる。
…1つは、暗殺前に島田一郎達から大久保宛に届いた暗殺予告の手紙の存在である。大久保は臆する事なく超然としていたというが、或る事が見えてくる…(私はあと10年はこの国の政治を牽引し、その後は後進にその職を渡す)と言った大久保は、その道が間近に断たれる危険性をその手紙から感じて、内心はその死を怖れていた事が見えてくる。
…もう1つは、もしその手紙の通り自分が暗殺されたならば、半年前に亡くなった盟友・西郷隆盛と、正に両雄相討ちの体となる…、という、恐怖と自負が入り交じった感情となり、それが間近に迫っている事による強迫観念となって、前島密から視た場合の予知夢的なものとなって現実化した、そのような事も見えてくるのである。
……展示室を見終えて警視庁を出ると、眼前には桜田門が雨に重く霞んで陰鬱に見えている。… (…そういえば、165年前に、正にこの前の広い道で水戸藩の浪士に大老の井伊直弼が暗殺されたな、…それをふと思い出した。……ある日、私の好きな作家で、史実を徹底的に調べる事で知られる吉村昭さんに警視庁から突然の問い合わせがあった。(桜田門外の変が在った場所を正確に知りたい)という内容である。…吉村さんは話した、(正にあなた達がいる警視庁の真ん前がその現場ですよ)と。
……唯のイメ-ジでなく、歴史の史実を知れば知るほど、現在に膨らみが見えて来て人生が面白くなってくる。…もっと知りたいという私の好奇心は、最近ますます強くなって来ているようである。……さぁ、次は何処に行こうか。

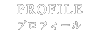
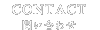
 ……1年前のこの日、私は日野に在る
……1年前のこの日、私は日野に在る …私はその髪を観ながら、間違いなく死ぬという明日の激戦を前に髪を形見に切った瞬間の土方の心境を想った。
…私はその髪を観ながら、間違いなく死ぬという明日の激戦を前に髪を形見に切った瞬間の土方の心境を想った。


 …いよいよ4月。…先日の桜の頃に、個展のために福井に行って来た。3日間の慌ただしい滞在であったが、故郷である事もあって久しぶりに会う人が多く、嬉しくも駆け抜けたような3日間であった。
…いよいよ4月。…先日の桜の頃に、個展のために福井に行って来た。3日間の慌ただしい滞在であったが、故郷である事もあって久しぶりに会う人が多く、嬉しくも駆け抜けたような3日間であった。 初日の夕方、福井に来たもう1つの大事な目的があった。日本の近・現代版画の主要な作品を数多くコレクションされているコレクタ-の
初日の夕方、福井に来たもう1つの大事な目的があった。日本の近・現代版画の主要な作品を数多くコレクションされているコレクタ-の




 …恩地孝四郎が描いたこのグロテスクな女達の不気味な相は、それを直に表した作品なのである。……今は無きこの銘酒屋にいた女郎たちはその数実に2000人はいたというから、浅草十二階下から拡がっているその様を迷宮といったのは誇張ではない。…室生犀星は(うつくしき瞳はみな招へども…)と美しい言葉で装おって書いているが、次の行の(こころ添いゆかず)は、リアルである。
…恩地孝四郎が描いたこのグロテスクな女達の不気味な相は、それを直に表した作品なのである。……今は無きこの銘酒屋にいた女郎たちはその数実に2000人はいたというから、浅草十二階下から拡がっているその様を迷宮といったのは誇張ではない。…室生犀星は(うつくしき瞳はみな招へども…)と美しい言葉で装おって書いているが、次の行の(こころ添いゆかず)は、リアルである。



 …この写真が特異なのは、(暗くて少し見えにくいかと思うが、)男の上に跨がった若い娘の背中で背負われている幼児(見た感じでは幼女)が、この激しい現場をじっと視ているという事である。…服装から推察すると時代は昭和12年頃か。…脇に投げ出された風呂敷包みが臨場感を醸し出している。…
…この写真が特異なのは、(暗くて少し見えにくいかと思うが、)男の上に跨がった若い娘の背中で背負われている幼児(見た感じでは幼女)が、この激しい現場をじっと視ているという事である。…服装から推察すると時代は昭和12年頃か。…脇に投げ出された風呂敷包みが臨場感を醸し出している。…

 ……およそ30分くらい経った頃であったか、私の進んで行く先の暗い繁みに富蔵さんが既に立っていた。見ると、おぉ‼とばかりに、その富蔵さんの目の先に件の高い石塀の連なりがあった。…そして、90年以上前の男女のその現場がその奥に今も暗いままに在った。正にあの写真そのままである。
……およそ30分くらい経った頃であったか、私の進んで行く先の暗い繁みに富蔵さんが既に立っていた。見ると、おぉ‼とばかりに、その富蔵さんの目の先に件の高い石塀の連なりがあった。…そして、90年以上前の男女のその現場がその奥に今も暗いままに在った。正にあの写真そのままである。
 ………写真のこの男女はその後、果たしてどういう人生を辿ったのであろうか⁉…時代からみて青年は戦死した可能性も高い。…そういえば、作家の
………写真のこの男女はその後、果たしてどういう人生を辿ったのであろうか⁉…時代からみて青年は戦死した可能性も高い。…そういえば、作家の
 ……
…… 先日、アトリエの片づけをしていたら、紛失したと思っていた2枚の写真が偶然出て来た。おぉ‼と思って、しばしその時の事を思い出していた。……今から30年前に行ったベルギ-の
先日、アトリエの片づけをしていたら、紛失したと思っていた2枚の写真が偶然出て来た。おぉ‼と思って、しばしその時の事を思い出していた。……今から30年前に行ったベルギ-の





 ゴッホ
ゴッホ


 …先ずはパリで客死した
…先ずはパリで客死した



 …果たして私が思った通り、井上さんは紛れもない本物の人物であった。…正に右袈裟斬りで切られたかのように井上さんは仰け反り、そして、後ろから誰かが鋭い気を放った事を瞬間に覚ったのであった。
…果たして私が思った通り、井上さんは紛れもない本物の人物であった。…正に右袈裟斬りで切られたかのように井上さんは仰け反り、そして、後ろから誰かが鋭い気を放った事を瞬間に覚ったのであった。
 …その翌日、私はJR日暮里駅で降りて、谷中銀座へと向かう御殿坂を上がっていった。…度々このブログに登場する田代富蔵さんが6月に個展を開催するので、その個展の為に書いたテクスト文を渡すのと新年の打ち合わせがその日の目的であった。……私はこの御殿坂を上がる度にいつも(一体何処に在ったのだろう!?)と思っている或る事があった。
…その翌日、私はJR日暮里駅で降りて、谷中銀座へと向かう御殿坂を上がっていった。…度々このブログに登場する田代富蔵さんが6月に個展を開催するので、その個展の為に書いたテクスト文を渡すのと新年の打ち合わせがその日の目的であった。……私はこの御殿坂を上がる度にいつも(一体何処に在ったのだろう!?)と思っている或る事があった。







 ………話を一変して物騒な事を書こう。…かつて
………話を一変して物騒な事を書こう。…かつて