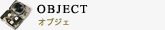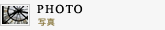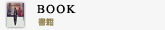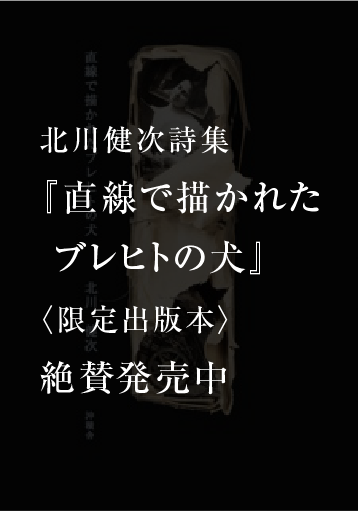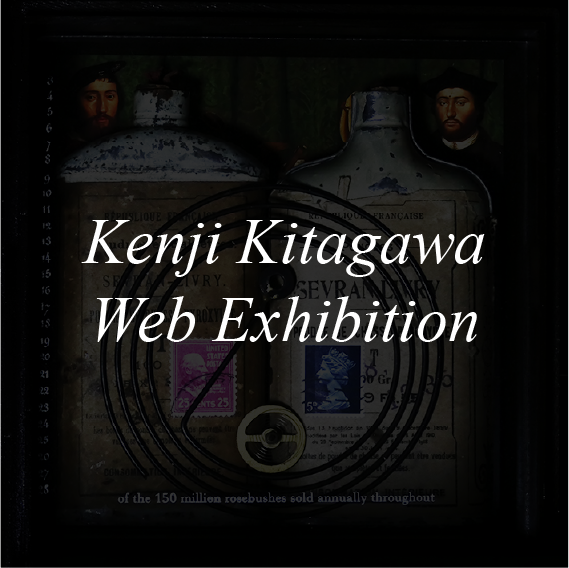…今回は平賀源内について書こうと思っていたが、意外や意外、前回のブログを読まれた人達から、ラストの終わり方が気になって仕方がない、実に面白いので、もう少し続きが読みたい‼…というメールがかなり反響として来たので、先ずはこの類い、…私以外に、予知能力、更には異常な交感能力を持っていた三人の人達について書く事から、今回のブログを始めようと思う。
 …先ずはパリで客死した佐伯祐三の話から。…1923(大正12)年9月1日、最初のパリ行きを控えた佐伯は家族や友人一行と信州渋温泉に滞在していたが、その前日に、近々に関東にかつてない大地震が来る事を直感的に予言して話していたという。
…先ずはパリで客死した佐伯祐三の話から。…1923(大正12)年9月1日、最初のパリ行きを控えた佐伯は家族や友人一行と信州渋温泉に滞在していたが、その前日に、近々に関東にかつてない大地震が来る事を直感的に予言して話していたという。
果たして翌日に未曾有の関東大震災が発生している。…これはパリで佐伯の最期を看取った親友の山田新一の証言にある。

佐伯祐三は時代が違うので残念ながら面識はないが、これから登場するお二人(駒井哲郎・井上有一)は実際に面識があり、またそこには私も絡んでいるという、ちょっと厄介な話。
……銅版画の詩人と云われた駒井哲郎さん(1920-1976)のお宅に、土方巽の弟子で、芸大で木版画を制作している友人のAと訪れたのは二十歳の頃であったかと思う。(大学で話し合うより、突っ込んだ話が出来るので、私達は度々訪れていたのである)。

…私達は版画の先達者の恩地孝四郎の画集を拡げながら、駒井さんと様々な意見を交わし合っていた。…今思えば、それは至福の体験であったのだが、私は分裂気味なところがあるらしく、意識の右側で駒井さんが熱心に語る恩地孝四郎論の話を熱く聞きながら、もう一方の左側では別な事を考えていたのであった。駒井さんのその広い家を眺めながら妄想に耽っていたのである。
(…いいなぁ、こんな天井の高い広い家に住めて、しかも美しい奥さんが出してくれるコ-ヒ-が実に美味しいではないか‼…それに引き換えどうだ、自分がいま住んでいる下宿は名前こそ『宝山荘』という立派な響きであるが、平屋で傾いていて…しかも暗い、…自分が大学を出たら、はたしてこんな広い家に住めるのだろうか?…ああ、いっそこの家に住んでみたいなぁ)…、二十歳の私はそう強く思ったのであった。…すると、Aと話していた駒井さんが、瞬間に何かを受け取ったらしく、突然私の方に顔の向きを変えてニヤリと無気味な笑みを浮かべながら、低い声でこう言ったのであった。(…俺が死んだら、この家に住めよ…‼)と。

…思っていた図星を指摘された私は驚いて駒井さんの顔を見た。…すると駒井さんは、笑うと写楽の絵のような凄みがあると云われている無気味な、もっと正しく謂えば、邪気に充ちた笑いをもう一度ニヤリと浮かべたのであった。…何も知らないAは、ただ私達のこの光景を呆然と眺めているだけであった。
…その後に出された天丼を食べながら私は思ったのであった。…これは読心術ではない。何故なら駒井さんはAと熱心に話し合っていた筈。だから私の顔の表情は視ていなかった。…とすれば、自分が出す何かが異常に強く、それをまた異常なまでに鋭く繊細な駒井さんの感性の受信能力と、まるで見えない電波のように交感してしまったのではないだろうか…。ともあれ、恐ろしくも不思議なそれは体験であった。
……それから4年後、24歳の私は池田満寿夫さんのプロデュ-スのおかげで、初めての個展を開催した。…版画の全作が完売となり、画廊との契約も順調にいき、個展の最終日に私は横浜の下宿へと帰った。…そこに一本の電話が入った。…駒井さんが舌癌肺転移のために築地の国立ガンセンタ-で逝去されたという知らせであった。

最後に登場する井上有一さん(1916-1985)は、国際的に高く評価された書家である。その突出した作品が放つ香気と狂気の様は他に類がない。…渋谷西武で『未来のアダム』という企画展が開催された折りに、私は出品作家として打ち合わせに行くと、そこに、同じく出品作家として来られた井上有一さんがおられた。
…それが出会いであるが、私は書の世界に疎く、そこで初めて井上さんの書を拝見したのであった。そして、その凄まじい集中力に私は唸った。…四谷シモンさんの人形や、建築家の坂茂さんなど様々な分野の作家を集めたこの展覧会のオ-プニングは盛況であった。
…そして会が終わり、三々五々、作家達もひきあげる時になった。…見ると、会場を出た通路の先を行く特徴のある後ろ姿が目に入った。……井上有一さんである。取り巻きに囲まれながら歩いているその後ろ姿を視て、邪気めいた悪戯を閃いた私は周りの友人達に(今から、ちょっと面白いものを見せるよ‼)と言って、前方を行く井上さんの右肩から左の背中に、一瞬の居合い切りの思いで強い〈気〉を放ったのであった。…(あれだけの作品を画く強い気を持った人物ならば、私のこの強い念は通じるに違いない‼)…そう思って、視えない、心中の刀で井上さんの背中を真っ二つに切り裂いたのである。
 …果たして私が思った通り、井上さんは紛れもない本物の人物であった。…正に右袈裟斬りで切られたかのように井上さんは仰け反り、そして、後ろから誰かが鋭い気を放った事を瞬間に覚ったのであった。
…果たして私が思った通り、井上さんは紛れもない本物の人物であった。…正に右袈裟斬りで切られたかのように井上さんは仰け反り、そして、後ろから誰かが鋭い気を放った事を瞬間に覚ったのであった。
…突然の事で驚いている周りの取り巻きに構わず、井上さんはその強い気を放った人物が誰なのかを確かめるべく、後ろを振り返って視たのであった。…そして、そこに私がいる事を知って、(ああ、あなたでしたか‼)と得心の笑みを浮かべながらお辞儀をしたので、私も笑ってお辞儀を返したのであった。
…私の友人達も唖然としていたが、それが井上さんとの最期の時であった。…………それを思い出すと、…まるで、平安京の朱雀大路で深夜にすれ違った二人の陰陽師のような体験で実に可笑しいのであるが、私はその時の事を時おり懐かしく思い出す時がある。
関東大震災を前日に正確に予知した佐伯祐三。…私の想いが空間を一瞬で跳んで駒井さんの感性に受信され、心中の言葉が、正確に伝わった事。…また私の放った強い気が、そのまま激痛となって井上さんが感受した事。…私の事はさておくとして、前述した佐伯祐三、駒井哲郎、…そして井上有一。…その三人の顔(特に眼)を視ると一つの共通点が見えて来る。…三人とも眼力(めぢから)が刺すように強いのである。…澁澤龍彦が何かのエッセイでそれについて『邪視』と表現して書いていたのを思い出す。邪視の持ち主こそが芸術家の証しであり、写真に残る特に十九世紀にはドラクロアなど、沢山の芸術家がみな邪視であったが、昨今は少なくなってしまったと。
………未だ生まれざる人と、既に死者となった人のために芸術は存在する、という意味の事をパウル・クレ-は書いているが、そもそも芸術とは語り得ぬ視えない物と人との豊かな交感現象である事を想えば、ここに書いてきた体験、更には前回のブログで書いた事は、全く不思議でも何でもなく、十分にあり得る事なのではないだろうか。
私事を語れば、…24才の時に、私の作品を初めて見た池田満寿夫さんは〈神経が剥き出しで表に出ている!〉と驚嘆し、また美術評論家の坂崎乙郞さんは、氏が関わっていた新宿の紀伊國屋画廊に持参した私の作品を視て、〈君の神経は鋭すぎる、このままでは精神が絶対に持たない!必ず破綻を起こす!〉と真顔で忠告してくれた事があった。…私は坂崎さんからの影響はかなり受けていて尊敬もしていたので、その忠告は胸に響くものがあった。自分でも、あまりに裸形な自分の神経を自在に御する事が出来ず、今想えばかなり辛かったのだと思う。
……紀伊國屋画廊の外に一歩出ると、街は若者たちの夜の雑踏で賑わっていた。その人群れの中を縫うように歩きながら私は自分に誓うように、こう呟いたのを覚えている。(…もう、短距離走者は止めた‼…これからは長距離走者で行こう‼)と。私は意志的な切り替えは速い。…そう意識を変えると、晴朗な気分に変わり、次第に制作への視点も変わっていった。…そして銅版画からオブジェへと表現の軸が変わり、美術に関する執筆活動、詩、写真…と表現の幅も拡がっていって、現在がある。…しかし、前回のブログで書いたように〈考えなくても直感的に突然視えてしまう!!〉という、この予知的な感覚だけは消える事がなく、ますますその頻度が増して今に来ているのである。
……次回のブログは、クレ-、ゴッホ、そして平賀源内について書く予定です。乞うご期待。

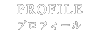
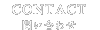

 …その翌日、私はJR日暮里駅で降りて、谷中銀座へと向かう御殿坂を上がっていった。…度々このブログに登場する田代富蔵さんが6月に個展を開催するので、その個展の為に書いたテクスト文を渡すのと新年の打ち合わせがその日の目的であった。……私はこの御殿坂を上がる度にいつも(一体何処に在ったのだろう!?)と思っている或る事があった。
…その翌日、私はJR日暮里駅で降りて、谷中銀座へと向かう御殿坂を上がっていった。…度々このブログに登場する田代富蔵さんが6月に個展を開催するので、その個展の為に書いたテクスト文を渡すのと新年の打ち合わせがその日の目的であった。……私はこの御殿坂を上がる度にいつも(一体何処に在ったのだろう!?)と思っている或る事があった。













-828x1024.jpg)
 …そんな慌ただしい中を先日、月刊美術の編集部から電話があり、
…そんな慌ただしい中を先日、月刊美術の編集部から電話があり、 …しかしそう多忙、多忙と言っていても人生はつまらない。忙中閑ありを信条とする私は、先日久しぶりに骨董市に行って来た。…今回はスコ-プ少年の異名を持つ、細密な作品を作り、このブログでも時々登場する
…しかしそう多忙、多忙と言っていても人生はつまらない。忙中閑ありを信条とする私は、先日久しぶりに骨董市に行って来た。…今回はスコ-プ少年の異名を持つ、細密な作品を作り、このブログでも時々登場する



 …東京の大井町線とJR南武線が交わる所に
…東京の大井町線とJR南武線が交わる所に