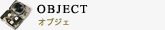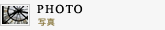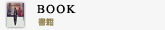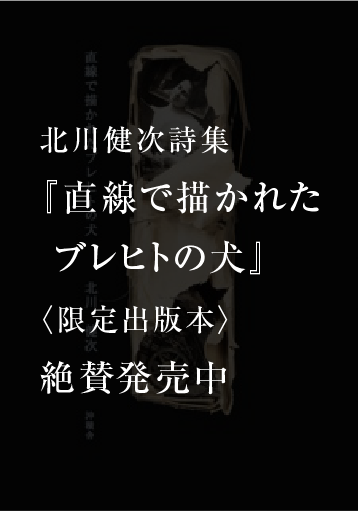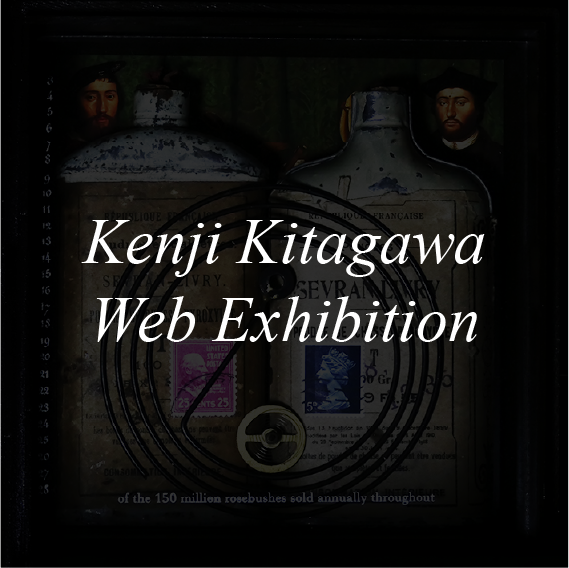…桜の花弁が散ったと思ったら、もう5月の足音が…。そしてますますの気象の乱高下が、今夏の更なる異常熱波の到来を不気味に暗示してでもいるような。
……さて、前回のブログでご紹介した福井のギャラリ-サライでの個展は今月末まで開催中であるが、…先日、雷雨の隙間を縫うようにして午前中に名古屋画廊に入り、夕方までかけて作品の展示に関わって来た。…5月は9日から24日まで、俳人で美術評論など他分野までも幅広く活動されている馬場駿吉さんとのヴェネツィアを舞台にした俳句と美術作品による二人展が開催され、また5月22日から6月9日迄は千葉の山口画廊で3回目の個展が開催されるのである。…画廊のオ-ナ-の山口雄一郎さんは毎回、作品の本質を見極めるような鋭い視点で長文のテクストを書かれるので、今回も私はそれを拝読するのを愉しみにしているのである。…このブログでは順を追ってご紹介する予定なので、次回のブログは、先ずは名古屋画廊での展覧会について詳しく書こうと思っている。
…さて、あなたがもし犯人に疑われ、警察の取調室で無罪を証明する為に1年前のこの日にどうしていたか⁉…と突然問われたら、その日の事を直ぐに思い出せるだろうか。…日記に書いてでもいない限り、まず即答は無理であろう。…しかし、私がいまブログを書いている4月21日に限っては、1年前のこの日に何をしていたかを即答出来る。…それほどに1年前の4月21日は記憶に強く残る日であった。
 ……1年前のこの日、私は日野に在る佐藤彦五郎新撰組資料館に行き、新撰組副長、土方歳三の生身の物を目撃するという体験をしていたのである。その物とは、新政府軍による箱館総攻撃で、土方が銃弾を浴びて亡くなる前日に、未だ少年だった小姓の市村鉄之助に、自分の写真、愛刀と共に土方の日野にある生家に届けるように命じた、土方が自分で切った形見としての遺髪であった。
……1年前のこの日、私は日野に在る佐藤彦五郎新撰組資料館に行き、新撰組副長、土方歳三の生身の物を目撃するという体験をしていたのである。その物とは、新政府軍による箱館総攻撃で、土方が銃弾を浴びて亡くなる前日に、未だ少年だった小姓の市村鉄之助に、自分の写真、愛刀と共に土方の日野にある生家に届けるように命じた、土方が自分で切った形見としての遺髪であった。
(…少年の市村鉄之助は、官軍の厳しい捜査網を掻い潜り、実に2年をかけて日野にある土方の生家に遺品を隠し持って辿り着いたが、その時の姿はまるで衰弱しきった悲惨な乞食のようであったという。)……その後、土方の写真や愛刀は折りにふれて公開されたが、遺髪だけは土方家の仏壇内に仕舞われたままで、その存在は今まで全く秘密であった。
………その秘密にされていた土方の遺髪の存在をずばり指摘したのは、死者の遺品、或いは行方不明者の持ち物に残る「残留思念」から、その時の状況を言い当てる事で知られる超能力者のジャッキ-・デニソンさんというイギリス人の女性である。…私はたまたま或る番組で、ジャッキ-さんが土方の子孫の前に座り、土方の刀に触れた後で、静かな、しかし確信を持った口調で、(もしかすると、この人の遺髪がある筈だ)とずばり言い当てて、子孫の人が驚愕するその場面を観ていたのであった。
…このジャッキ-さんのような、残留思念から不明者の様々な事を透視する能力が確かに存在する事は以前から知っていた。……残留遺物から事件の真相(例えば誘拐犯人の居場所や死体遺棄現場……など)を突き当てる捜査法が、欧米の警察捜査では実際に活用されている事はつとに知られているが、ジャッキ-さんの持っている透視能力は特に突出している感がある。…ちなみに、このブログでも度々書いているが、私は予知的な能力、或いは強度な「気」を発する、更には瞬時に離れた場所から物事の本質を視ぬいてしまう直感力…などといった能力は多分に持っているが、ジャッキ-さんのように残留思念から捜査の対象者の当時の事柄を透かし視るという能力は、私とは違うまた別なものである。…
その土方歳三の形見の遺髪が初公開されるという2024年の4月21日。…日野にある佐藤彦五郎新撰組資料館の前は、そのテレビ番組を観て、公開日を知って訪れた人、人、人…で溢れていた。資料館の人の話では、公開日は限定した数日間に限られていたが、1日で約6000人もの人が全国から訪れているという。…私が行ったその日も整理券が配られて、…遠方から遙々来ても入れない人もいるという状況であった。
私達の列が観れる番が来たが、限られた見学時間は僅かに10分。…近藤勇、沖田総司、永倉新八、…等々の書簡、土方の愛刀、写真(複写)…と順に展示されている別な場所に、件のその束ねた遺髪が白紙の上に展示されていた。
 …私はその髪を観ながら、間違いなく死ぬという明日の激戦を前に髪を形見に切った瞬間の土方の心境を想った。
…私はその髪を観ながら、間違いなく死ぬという明日の激戦を前に髪を形見に切った瞬間の土方の心境を想った。
そして、その束ねた毛髪からは、池田屋事件時の叫びや長州人の断末魔の怒声、鳥羽伏見の闘いの時の大砲の破裂音や硝煙の匂いさえも透かし視るように伝わって来るのであった。
…熱くなって覚えたこの感覚の先に、ジャッキ-デニソンさんには、残留遺物からの様々な事が見えてくるのであろう。
………ふと気がつくと、遺髪を観ている私のすぐ横に、たいそう美しい女性が静かに立っていた。その顔を見て…土方歳三の子孫だと直感したので、(もしかして子孫の方ですか?)と問うと、果たしてそうであった。…私は好機と思い、以前からずっと気になっていた或る事を確認したく、その方に訊いてみた。(…実はものの本で知ったのですが、市村鉄之助が隠し持って来た土方歳三の写真の実物には、その写真の端を噛んだ土方の歯跡が残っていると書いてありましたが本当でしょうか⁉)と。
………………女性の方は、おそらくは今まで誰も訊いて来なかったであろうこの質問に一瞬戸惑ったようであったが、(……うっすらですが、その写真には土方の歯跡が今も確かに残っています)と答えてくれた。……やはりそうであったか。……私は写真の端に付いているというその歯跡こそ、土方の生きた証と矜持を映す物であると常々思っていたのであるが、今まで機会ある度に見た写真の複製には写っていなく、或いは伝説上の話かとも思っていたのであるが、タイミングよく子孫の方に直に訊けて得心したのであった。
………(新撰組で一番恐かったのは、それはもう副長の土方歳三です。隊列の先頭で歩いて来る、あんな鋭い眼をした人は今も忘れる事は出来ません。) ……司馬遼太郎が書くずっと以前に、作家の子母澤寛が、土方歳三を目撃したという、当時まだ存命中だった京の街に住んでいた老婆から訊いた覚え書きには、そのようにある。…幕末史に詳しい人でも、西郷隆盛暗殺未遂事件というのがあった事を知る人は案外少ないのではないだろうか。…

その暗殺未遂事件、単独で仕掛けたのは誰あろう、土方歳三である。…実行したのも土方歳三ただ一人(近藤も沖田も関わっていない幕末遺聞の閉ざされた一頁。)…土方は一人、平服で待機しており、薩摩藩邸から出て来た大男を視るや、通り越し時に抜き胴で一瞬で仕留めたが、それは西郷ではなく別人であった。
もしこの時、西郷本人であったら間違いなく明治維新は無く、徳川政権が続いた事は必至であろう。幕府の最大の敵になるのは西郷隆盛である事を、土方は早々と明察して、単独で暗殺を謀ったのである。

…今回のブログは土方歳三のその豪胆な話と先見性に詳しく言及したかったのであるが、信号が赤く点ってしまった。…どうやらブログの分量が尽きてしまったようである。

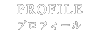
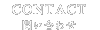



 個展の時に、会場で何人かの人から、
個展の時に、会場で何人かの人から、
 歌舞伎の『女車引』は、
歌舞伎の『女車引』は、 翌日に観た
翌日に観た ……幼年期の仕舞われた記憶が突然蘇るのは何も視覚だけとは限らない。聴覚、嗅覚、触覚、更にはふと覚えた微かな気配からも記憶が蘇る時がある。……
……幼年期の仕舞われた記憶が突然蘇るのは何も視覚だけとは限らない。聴覚、嗅覚、触覚、更にはふと覚えた微かな気配からも記憶が蘇る時がある。……