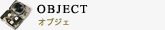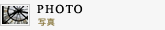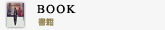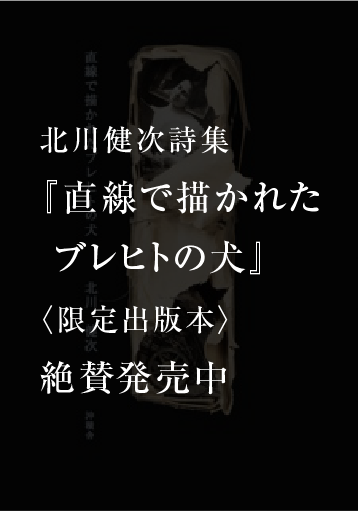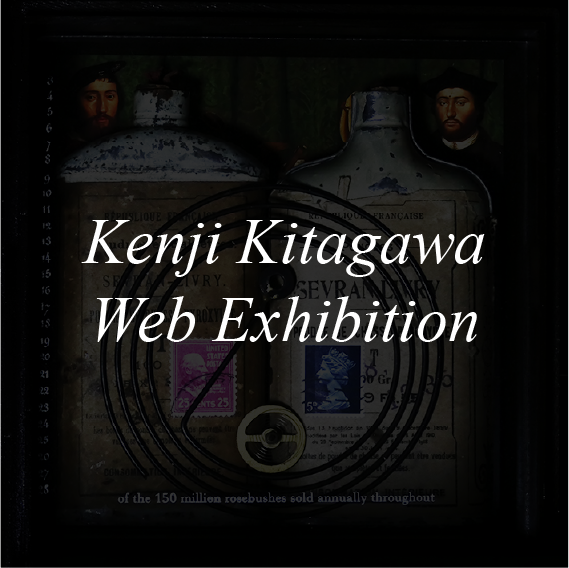先日の19日に荻窪の劇場カラスアパラタスに行き、勅使川原三郎さんと佐東利穂子さんによるダンス公演『ケイジの夢』を観た。…真っ暗な会場の舞台の上に垂直に朧な光が射しこむと左右にマヌカンのような気配を持った演者である二人が立っている。完璧なその美しい立ち位置の配置に先ず息をのむ。…そこから既に立ち上がっている緊張感は、かつてマルセル・デュシャンが(名人が配したチェス盤上の駒の配置は実に美しい)と語った、その美しさを想起する。
…また、満席で埋まった観客席に鋭く突き刺してくるその緊張感は、詩人・日夏耿之介の(己が頭脳は千百の思考の銀線で悉く/張り裂けさうであるところへ/水晶体は多彩多淫の光塵にて/……)という詩行の、正にそれである。…勅使川原さんの、時に犯意を多分に帯びたグロテスク、時にロマネスク、時にアルカイック…と妖しい身体表現の多彩な様が展開し、それに対演するように佐東利穂子さんの優美にして妖しい身体の動きが相乗して、ますますの膨らみを呈する中、そこにケイジの「夢」の緩やかにして眠るように虚ろな幻聴のような音が聴覚から忍び入って来て、私達はかつて覚えた事のない体感を各々の感性のまま各々の孤独の内に享受するのである。
……一瞬の隙もないこの緊張感の持続はおよそ一時間続き、最後の正に最後の暗転直前に、勅使川原さんが光の中で見せた〈一瞬の振り返り〉という所作によって、その一瞬後に美しい幻の残像となって、この作品は完成度の高さを極めるように、鮮やかに紡ぎ終えるのである。
 ………話を一変して物騒な事を書こう。…かつて三島由紀夫は、切腹する時の刃の様をこう語った事がある。…〈刀が体内に入るのではなく、体内にそれは出るのである〉と。…私がこの〈出るのである!〉と書かれた文章を読んだ時に覚えた戦慄は今も生々しく覚えている。…マゾヒズムの極地、被虐的なエロティシズムと狂気の混合、或いはやがて本人が突き刺す時の気合いの映しか⁉…三島が現代の定家と評した天才歌人の春日井建の歌にも、さすがにここまでのイメ-ジの言及は無い。
………話を一変して物騒な事を書こう。…かつて三島由紀夫は、切腹する時の刃の様をこう語った事がある。…〈刀が体内に入るのではなく、体内にそれは出るのである〉と。…私がこの〈出るのである!〉と書かれた文章を読んだ時に覚えた戦慄は今も生々しく覚えている。…マゾヒズムの極地、被虐的なエロティシズムと狂気の混合、或いはやがて本人が突き刺す時の気合いの映しか⁉…三島が現代の定家と評した天才歌人の春日井建の歌にも、さすがにここまでのイメ-ジの言及は無い。
……それともう一つ。…周知のように、この宇宙はわかっているだけでも11次元あるというが、私達が感覚として実感出来るのは僅かにこの3次元だけである。身体内部もまた広大無辺な宇宙として捕らえ、そこに11次元的な考察をする事から見えてくる事の可能性の数々。……また、A4用紙の両端の左右に点を打つと、各々の点は左右に離れているが2つ折りにすると、この2点は一瞬で重なって最短の関係となる。
…………私は勅使川原三郎という稀人が全く独自に編み出したダンスメソッドについて時に好奇心を持って想像するのであるが、それをダンスではなく詩法の一つの可能性として考えている。…今述べた、三島の特異な身体感覚、宇宙の11次元的構造、紙上の2つの点の重なり……等々。これらも含めて様々な角度からの詩的イメ-ジの出現として捕らえ、その想像の権能から身体感覚へと移し変えているのではあるまいか、…そんな想像さえも、自分の制作の合間に想像してみるのである。そしてそれは自分の作品制作にも及んで来て、実に有益な時間でもあるのである。
………荻窪の劇場カラスアパラタスに行くと地階が公演会場であるが、私は1階の奥に展示してある勅使川原さんの毎回の新作素描を先ずじっくりと拝見するのを楽しみにしている。…来場した観客達は地階へと急いで、その素描の存在には気付いていないようであるが、私は実に興味津々に新作の素描に見入るのである。…世界素描大全という画集がもしあるとしたら、その全集に収まる事のない危ういまでに逸脱したその素描は必見である。
…あえて近似値を探すとしたら、人間の人体構造の仕組みを冷徹な迄に追及して描写したダ・ヴィンチが近いか、…或いは少女の腕の傷口に偏執したヴォルスのそれか。…とまれ勅使川原さんの素描を例えるならば、手術用の薄いゴム手袋を裏返した、その生々しさに或いは近いかもしれない。…それまで裏側の日影的な存在だったゴムの皮膚が急に表にされた事で、恥じらうように熱や匂いを放射して、腐臭さえも伝わって来るような、…そして腑分けされた肉の積み重ねられた素描の中に出現する幼児、時に胎児のままの姿と化した彼自身の肖像を前にする時、あたかもダンスという美的犯意の現場に遺された、犯人の姿を垣間見れるヒントのようで実に興味深いのである。
そして、真に彼は中原中也が記した、物が名辞される以前の感覚を温存したままに感性が息づいている稀人(つまりは本当の詩人)なのだと思うのである。
………『失踪したフィレンツェの或る屠殺執行人が遺した犯罪忘備録』…私は勝手にそう呼んで拝見している、この膨大な素描の山は、天才勅使川原三郎を知る、興味深いヒントなのである。
………ヴェネツィア・ビエンナ-レで金獅子功労賞を授賞して以降、更に海外からの公演依頼が殺到し、2月からは、プラハ・そしてミラノなどのイタリア三都市・ロンドン・セルビア・オランダと公演が続くので、次回の日本での公演は4月26日からである。
………アトリエには知人や未知の美術家からの個展案内状が届くが、申し訳ないが私は殆ど観に行かない。人生という短い時間の中で、無駄には過ごしたくないからである。…しかし、この荻窪にある劇場カラスアパラタスには余程の事がない限り私は通いつめ、既に10年以上の時が経つ。早いものである。…何故行くのか⁉…理由は簡単で、それが至純に美しく、紛れもなく本物の芸術だからである。

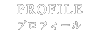
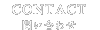
 …『週刊ポスト』で、私と
…『週刊ポスト』で、私と …当時刊行したばかりの拙著
…当時刊行したばかりの拙著

 さて話は変わって、今度はカニの話を。……先日、私の故郷の福井から
さて話は変わって、今度はカニの話を。……先日、私の故郷の福井から
 ………そして、カニと蜘蛛が先祖は同じだという説があるのを思い出し、タブレットで両者の顔を比較した。蜘蛛の顔を初めて視たが、こちらもゾッとする。
………そして、カニと蜘蛛が先祖は同じだという説があるのを思い出し、タブレットで両者の顔を比較した。蜘蛛の顔を初めて視たが、こちらもゾッとする。



 …
…


 …川端のもう一つの代表作は
…川端のもう一つの代表作は …さて、その猪瀬の本が出る遥か前に、一人の美大の学生が、中伊豆のその
…さて、その猪瀬の本が出る遥か前に、一人の美大の学生が、中伊豆のその

 …さて急いで結論に入ろう。…私はこう考える。…つまり川端自身が当初思っていた以上に作品は独り歩きを始め、いつしか作者を離れて『雪国』は川端の生涯を代表する名作であるばかりか、日本の近代文学を代表する名作となっていった。
…さて急いで結論に入ろう。…私はこう考える。…つまり川端自身が当初思っていた以上に作品は独り歩きを始め、いつしか作者を離れて『雪国』は川端の生涯を代表する名作であるばかりか、日本の近代文学を代表する名作となっていった。




 持った台風へといよいよその狂暴さを増していく事は必至である。…(ここはヴェネツィアか⁉)と映るほどに、特に東日本は水都(いや廃都)と化し、車が水に漬かっている光景が、もはや日常的になって来た。
持った台風へといよいよその狂暴さを増していく事は必至である。…(ここはヴェネツィアか⁉)と映るほどに、特に東日本は水都(いや廃都)と化し、車が水に漬かっている光景が、もはや日常的になって来た。
 高山宏氏から自由に書いてほしいと言われたので、私は
高山宏氏から自由に書いてほしいと言われたので、私は



 …私がその時に持っていたのは、作家の
…私がその時に持っていたのは、作家の

 …横浜山手の根岸の坂を上がった所に、相模湾を眺望できるレストランがある。荒井由美(松任谷)の初期の代表曲『海を見ていた午後』の舞台となったレストラン
…横浜山手の根岸の坂を上がった所に、相模湾を眺望できるレストランがある。荒井由美(松任谷)の初期の代表曲『海を見ていた午後』の舞台となったレストラン …墓参して引き返す時に、面白い光景が目に入った。…寺の塀に沿って夥しい数の卒塔婆がズラリと立ち並んでいるのである。その向かい側にはすぐに家々が建っていて、明らかに、その部屋から見える朝からの光景は、障子や窓越しに並んで立っている、
…墓参して引き返す時に、面白い光景が目に入った。…寺の塀に沿って夥しい数の卒塔婆がズラリと立ち並んでいるのである。その向かい側にはすぐに家々が建っていて、明らかに、その部屋から見える朝からの光景は、障子や窓越しに並んで立っている、






 2日後の22日に、
2日後の22日に、
 …東京の大井町線とJR南武線が交わる所に
…東京の大井町線とJR南武線が交わる所に