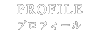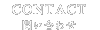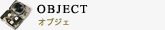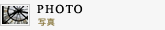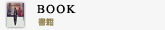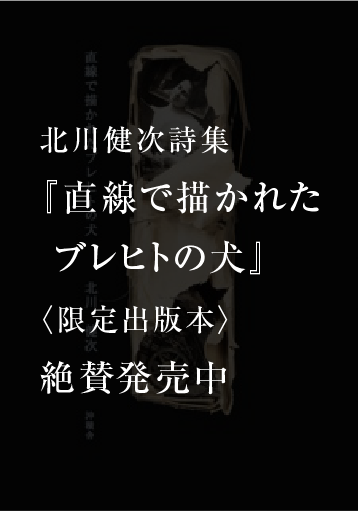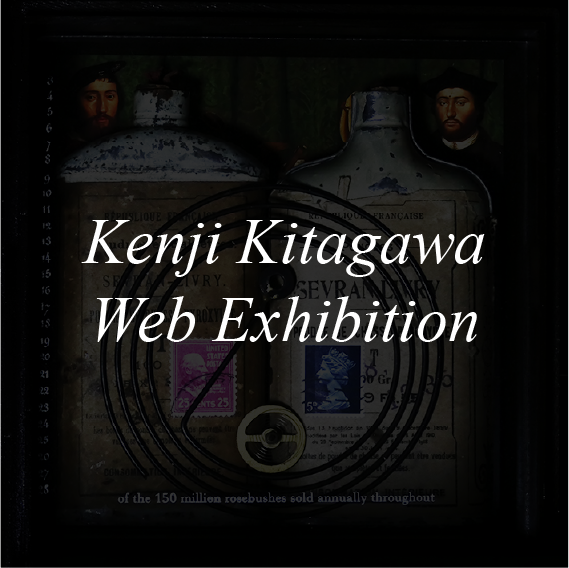20世紀に大きな足跡を遺した人物として浮かぶのは、アインシュタインやトルストイ、、チャップリン…等々さまざまな人物がいるが、先ず筆頭に指を折って想い浮かべるのは、やはりパブロ・ピカソ(1881-1973)の存在かもしれない。ピカソの作品の中に、ミノタウロス(ギリシャ神話に登場する牛頭人身の怪物)を主題としたものが幾つかあるが、あたかも自身を映した自画像として描かれたようなその異形な怪物性をもって、ピカソは全くぶれる事なく、この激動の世紀を、幾度もの羽化を経るようにして生きぬいたのであった。しかし、画家の代名詞的な存在として、20世紀のイコンのように誰もがその名前を知っていながらも、ピカソの私生活がいかなるものであったかを知る者は皆無であると言っていい。ピカソ=ペルソナ(仮面)、この表現が符合するように、その実人生は知られざる深い謎に満ちているのである。
20世紀に大きな足跡を遺した人物として浮かぶのは、アインシュタインやトルストイ、、チャップリン…等々さまざまな人物がいるが、先ず筆頭に指を折って想い浮かべるのは、やはりパブロ・ピカソ(1881-1973)の存在かもしれない。ピカソの作品の中に、ミノタウロス(ギリシャ神話に登場する牛頭人身の怪物)を主題としたものが幾つかあるが、あたかも自身を映した自画像として描かれたようなその異形な怪物性をもって、ピカソは全くぶれる事なく、この激動の世紀を、幾度もの羽化を経るようにして生きぬいたのであった。しかし、画家の代名詞的な存在として、20世紀のイコンのように誰もがその名前を知っていながらも、ピカソの私生活がいかなるものであったかを知る者は皆無であると言っていい。ピカソ=ペルソナ(仮面)、この表現が符合するように、その実人生は知られざる深い謎に満ちているのである。
その謎の暗部に光を照射するような興味深い翻訳本が最近刊行された。『ピカソの世紀』の続編で、著者はピエ-ル・カバンヌ(フランスの美術批評家で、フェルメ-ルやデュシャン他の研究書も多い)、訳者は中村隆夫氏(『象徴主義:モダニズムへの警鐘』、『バロックの魅力』などの著作のほか展覧会の監修も多い)、刊行は西村書店。 パリのピカソ美術館で最も売れているというだけに確かに記述は微細に渡り、私達がピカソについて外周のイメージでしか知り得ていなかった事に慄然とさせられる。
前作の『ピカソの世紀』はあまりに面白く、このメッセージ欄で私はその本を紹介した事があるが、その続編の刊行を私は久しく待ち望んでいたのであった。それが漸くにして刊行されたのである。…この二冊を合わせると厚さは10センチくらいの文量になるが、訳者の中村氏の訳は極めて的確精緻な文章で、訳書である事を忘れるほどに文章が練られていて読みやすい。…私見であるが、ピカソの主題は常に私小説的なものであったが、1910年の夏、スペインのカダケスという寒村(ダリのアトリエもある)にて、キュビスム表現の極(つまり、人類初の抽象絵画誕生の萌芽直前)に至りながらも、彼はその先に自身の崩壊がある事を直観し、具象性に戻るのであるが、この認識と自己分析の正確さの中に私はピカソの真の天才性を見る。−この事は拙著『モナリザミステリー』に所収された「停止する永遠の正午-カダケス」にて言及済みであるが、ともあれ、今、ピカソを読む事の意味には、人間性の矛盾がグロテスクに露出した20世紀という時代の相貌を直視する事にも繋がっていて興味の尽きない本である。…ぜひのご一読をお勧めする次第である。