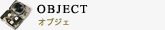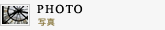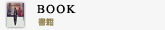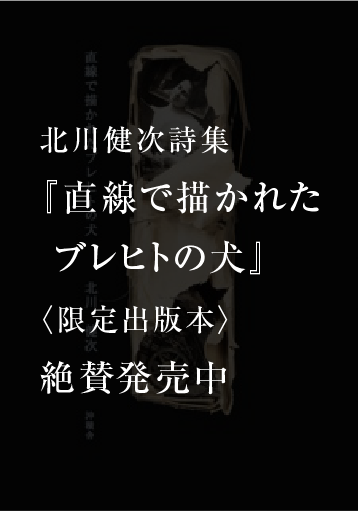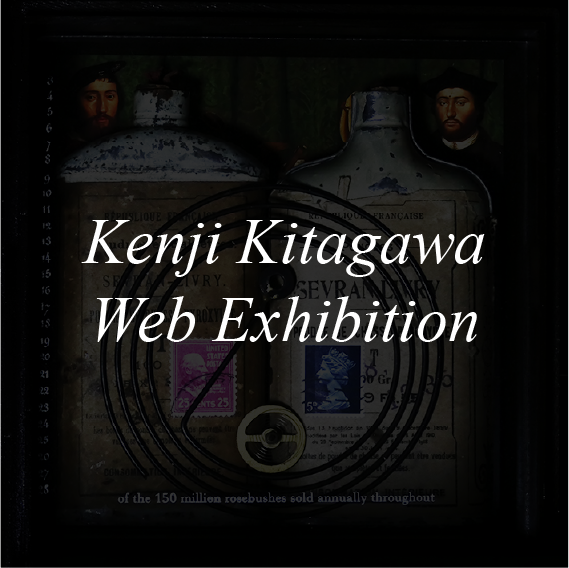暑いを通り越して、早くも酷暑の日々である。あきらかに地球全体の気象のリズムが温暖化によって狂いを呈している為に、私たちの遺伝子に組み込まれている〈夏〉に抗するプログラムは、かつてない異常な現象を前にして悲鳴をあげているようである。そのような中で、集中的にコラージュの制作をし、今はオブジェのそれに移っている。来春までに十近い数の個展が入っているので、その制作に専念の日々である。
さて、ここ数日にかけて私の作品を装画にした本が次々と刊行されてアトリエに届いた。『ガウス数論論文集』(ちくま学芸文庫)、『ゴースト・ハント』(創元推理文庫)、『夜毎に石の橋の下で』(国書刊行会)。『ゴースト・ハント』は刊行してすぐに増刷が決まった由。この本と『夜毎に石の橋の下で』の装幀は、中島かほるさんである。中島さんとは、久世光彦氏との共著『死のある風景』(新潮社)以来ずいぶんと私の作品を装画化して、エレガントで高い美意識を映した装幀をされている。私は中島さんの感性が大好きで、いつも出来上がりを楽しみにしている。今回の二冊は版画と写真であるが、各々の異なったメチエへのこだわりを、各々の小説の主題と絡ませて浮彫りをするように眼前に立ち上がらせている。『ガウス数論論文集』の装幀をされた神田昇和氏は、このガウスのシリーズで私のオブジェが持つ秘めたメッセージを抽出し、ガウスの難解な定理や法則と通底するように、ミリ単位の見事なトリミングをされている。中島かほるさん、神田昇和氏、共に私が最も信頼している数少ない装幀家の方々である。
英国怪奇小説の最後の名手と評されるH・R・ウェイクフィールドによる『ゴースト・ハント』の18の短編はかなりリアルで凄まじいまでに怖い。暑気払いには最高である。『夜毎に石の橋の下で』は、ルドルフ二世時代の魔術都市ブラハが舞台の幻想小説である。海外での次の写真撮影の候補地として、パリ、上海、そしてプラハを考えていただけに、本が届いてからすぐに私はこの本に読み耽った。イメージの立ち上げとして私を導いてくれる面白さを多分にこの小説は持っている。ー 私はそう感じた。三冊各々にご興味のある方にはぜひ御一読を、お勧めしたい本である。

夜毎に石の橋の下で

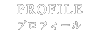
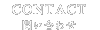


 私のオブジェ作品を表紙の装画に使った
私のオブジェ作品を表紙の装画に使った