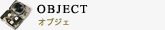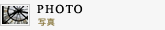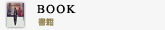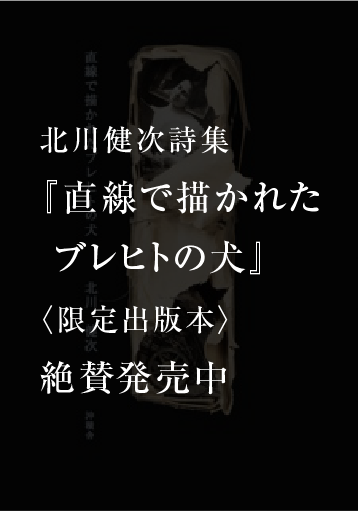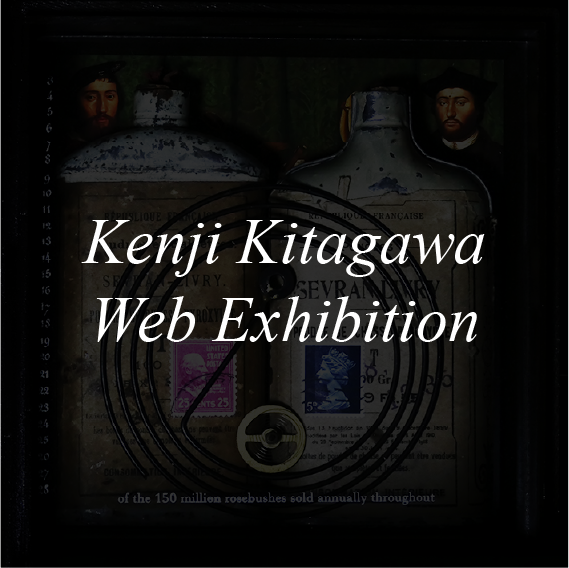……作品の制作中はアトリエの中は全くの無音であるが、寛いでいる時はレコ―ドを聴く事が多い。脳のリセットに丁度良い。……最近は専らジュリエット・グレコを聴いている。曲で特に気に入っているのは『あとには何もない』という曲。低音の艶を帯びたグレコが歌い紡ぐ、過ぎ去りしサンジェルマン・デ・プレのノスタルジックな情景は、留学時にそこに住んでいた時を彷彿とさせ、風景や街の匂いまでがありありと浮かんで来て懐かしい。
……作品の制作中はアトリエの中は全くの無音であるが、寛いでいる時はレコ―ドを聴く事が多い。脳のリセットに丁度良い。……最近は専らジュリエット・グレコを聴いている。曲で特に気に入っているのは『あとには何もない』という曲。低音の艶を帯びたグレコが歌い紡ぐ、過ぎ去りしサンジェルマン・デ・プレのノスタルジックな情景は、留学時にそこに住んでいた時を彷彿とさせ、風景や街の匂いまでがありありと浮かんで来て懐かしい。
聴きながらアトリエの外の桜の樹に目をやると、満開を過ぎて散りゆく桜花が美しい。…時おり、通行人がそれを撮影しているのが目に映る。
……桜と言えば、幕末に坂本龍馬が好んで唄った都々逸に「咲いた桜になぜ駒つなぐ/駒が勇めば花が散る」というのがある。元々は伊勢の民謡で男女の事を謳った卑俗な唄らしいが、龍馬は薩摩の島津久光の命令で起きてしまった「寺田屋事件」の悲惨な同士討ちへの憤りを嘆いて度々三味線を弾きながら唄ったという。…曲本来の意味を変える、引用と見立てのセンスが龍馬は抜群である。……龍馬自作の都々逸は「何をくよくよ川端柳/川の流れを見て暮らす」というのがある。実に粋であるが、粋と云えば、長州の暴れ馬、高杉晋作の作った都々逸「三千世界の烏を殺し、主と朝寝がしてみたい」もなかなか秀逸である。
幕末の変革を起爆的かつ実質的に変えたのは、西郷隆盛、坂本龍馬、高杉晋作の三人の行動力であるが、その中の二人が共に風狂な諧謔精神を多分に持っていた事は興味深い。この二人に共通していたのは即興の力であり、機敏―即ち、機を視るに敏の能力が、長州の藩論を一気に倒幕へと動かした巧山寺挙兵の高杉晋作のク―デタ―、また坂本龍馬の薩長連合や大政奉還の仕掛けへと繋がっていった事は周知の通り。……桜について色っぽく書こうと思っていたら、また熱くなってしまったので、ここで少しく話題を変えよう。
 先日、京都の観光名物の一つ、亀岡から嵐山へと流れる保津川を舟で行く「保津川下り」で船頭の棹(さお)の操作ミスにより舟が岩に激突し座礁して転覆、四人乗っていた船頭の内の一人が死亡、もう一人の船頭が今も行方不明という事故が起きた。乗客25名はライフジャケットを着けていたので無事であったという。
先日、京都の観光名物の一つ、亀岡から嵐山へと流れる保津川を舟で行く「保津川下り」で船頭の棹(さお)の操作ミスにより舟が岩に激突し座礁して転覆、四人乗っていた船頭の内の一人が死亡、もう一人の船頭が今も行方不明という事故が起きた。乗客25名はライフジャケットを着けていたので無事であったという。
……私はこの事故の詳細を知ってゾッとした。今から30年前の春、桜の花見時に京都にいて、この保津川下りを体験していたからである。ゾッとしたのは他でもない。私が乗った時はライフジャケットなど無く、もしその時に転覆事故が起きていたら果たして……と思ったからである。
亀岡を出発して終点の嵐山・渡月橋まで舟で行く距離は16Km、およそ二時間の舟旅である。……私は数名の知人と一緒に乗っていた。桜が満開の時で風景が華やいでおり、乗客はみな浮かれ気分であった。……江戸時代から、嵐山遊山の名物の一つであった、この保津川下り。船頭の巧みな技で、川の巨大な岩々に棹を当てて漕いで行くのであるが、その棹を岩に当てるポイントが決まっている為に、長年の時を経て、その岩に棹の当たる所に穴が出来ている。それ程に永い歴史をこの観光名所は持っているのである。
…………最初は流れが緩やかなので、船頭が客に「誰か棹を操ってみませんか?」と楽しそうに言う。すると、私が乗っていた時は中年の主婦らしき人が勇んで手を挙げ「私、やります!」と言って立ち上がり、棹を操ってみせた。なかなか上手い。……すると船頭が「さすがお客さん、人妻だけに棹(竿)の扱いが実に上手い!」と下ネタのジョ―クを言って笑わせた。……鴨にされたその主婦はふくれるが回りは爆笑。おばさん達も笑っている。ある意味それも恐いが……。思うにこの船頭、毎日飽きもせず、このネタで楽しんでいるのだろうな、と思ってみたりもする。
……さらに舟が行く。……私は舟に乗りながら、昭和25年7月3日に、この保津川に、乗っていた山陰本線の列車から真っ逆さまに飛び降りて死んだ一人の女性・林志満子の事を想っていた。〈昭和25年〉、〈林〉……この2つの言葉でピンと来たら、その人の連想力は刑事級であるかと思う。……先を急ごう。……林志満子、……昭和25年の7月2日の深夜に金閣寺を焼いた林養賢の母親の名前である。……事件翌朝、舞鶴から駆けつけ、牢獄にいる息子に面会を求めたが息子に拒絶され、その帰途に母は列車から、……私達がいるこの保津川に投身して果てたのである。……『金閣寺』を刊行した直後に対談した三島由紀夫と小林秀雄との会話の中で、この保津川の寂しい景色の事を(静まり返った不思議な所)と二人が共に語った箇所を読んでいて、いつかその場所に行ってみたいと思っていたのである。
 ……………………「さぁ、これからがスリル満点の荒々しい場所に入りますからね。皆さん覚悟はいいですかぁ!」と船頭が大声で言って、最大の難所―大高瀬という流れの激しい場所に舟が入って行く。……この度の転覆死亡事故はそこで起きたのであった。「事故はやはりあすこで起きたのか!」
……………………「さぁ、これからがスリル満点の荒々しい場所に入りますからね。皆さん覚悟はいいですかぁ!」と船頭が大声で言って、最大の難所―大高瀬という流れの激しい場所に舟が入って行く。……この度の転覆死亡事故はそこで起きたのであった。「事故はやはりあすこで起きたのか!」 ……当然だなと思う程に今もありありとその時の光景が浮かんで来る、そこは激しい急流なのである。だから、その難所を経て流れは次第に穏やかになり、終点の嵐山の渡月橋が正に大観の「生々流転」の縮図、劇のカタルシスのように効果的に見えて来るのである。……
……当然だなと思う程に今もありありとその時の光景が浮かんで来る、そこは激しい急流なのである。だから、その難所を経て流れは次第に穏やかになり、終点の嵐山の渡月橋が正に大観の「生々流転」の縮図、劇のカタルシスのように効果的に見えて来るのである。……
今回のブログは、タイトルにあるように橘夫人が登場する予定であったが、桜にまつわるエトセトラにくわれてしまい、どうやら出番を見失って、小栗虫太郎の小説の行間の中に入っていってしまったようである。橘夫人には、またいつか登場して頂く事にしよう。




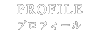
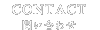
 ……作品の制作中はアトリエの中は全くの無音であるが、寛いでいる時はレコ―ドを聴く事が多い。脳のリセットに丁度良い。……最近は専ら
……作品の制作中はアトリエの中は全くの無音であるが、寛いでいる時はレコ―ドを聴く事が多い。脳のリセットに丁度良い。……最近は専ら 先日、京都の観光名物の一つ、亀岡から嵐山へと流れる保津川を舟で行く
先日、京都の観光名物の一つ、亀岡から嵐山へと流れる保津川を舟で行く
 ……………………「さぁ、これからがスリル満点の荒々しい場所に入りますからね。皆さん覚悟はいいですかぁ!」と船頭が大声で言って、最大の難所―大高瀬という流れの激しい場所に舟が入って行く。……この度の転覆死亡事故はそこで起きたのであった。「事故はやはりあすこで起きたのか!」
……………………「さぁ、これからがスリル満点の荒々しい場所に入りますからね。皆さん覚悟はいいですかぁ!」と船頭が大声で言って、最大の難所―大高瀬という流れの激しい場所に舟が入って行く。……この度の転覆死亡事故はそこで起きたのであった。「事故はやはりあすこで起きたのか!」 ……当然だなと思う程に今もありありとその時の光景が浮かんで来る、そこは激しい急流なのである。だから、その難所を経て流れは次第に穏やかになり、終点の嵐山の渡月橋が正に大観の「生々流転」の縮図、劇のカタルシスのように効果的に見えて来るのである。……
……当然だなと思う程に今もありありとその時の光景が浮かんで来る、そこは激しい急流なのである。だから、その難所を経て流れは次第に穏やかになり、終点の嵐山の渡月橋が正に大観の「生々流転」の縮図、劇のカタルシスのように効果的に見えて来るのである。…… ……制作が終わり、眠る前には本を読む習慣であるが、最近は座談集を読むことが多い。なんとも深い眠りに入っていけるのである。……先日読んで面白かったのは、哲学者の『
……制作が終わり、眠る前には本を読む習慣であるが、最近は座談集を読むことが多い。なんとも深い眠りに入っていけるのである。……先日読んで面白かったのは、哲学者の『



 …………
………… 坂本龍馬がブームであるが、実像はどうであったか。
坂本龍馬がブームであるが、実像はどうであったか。