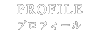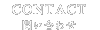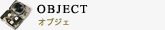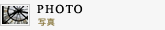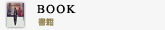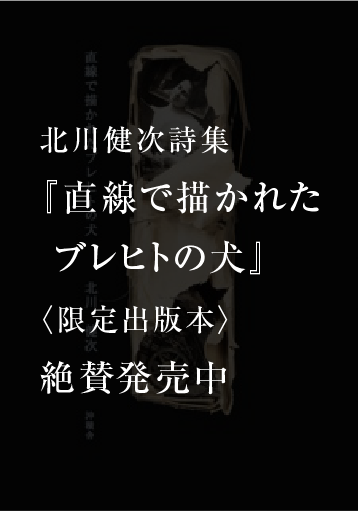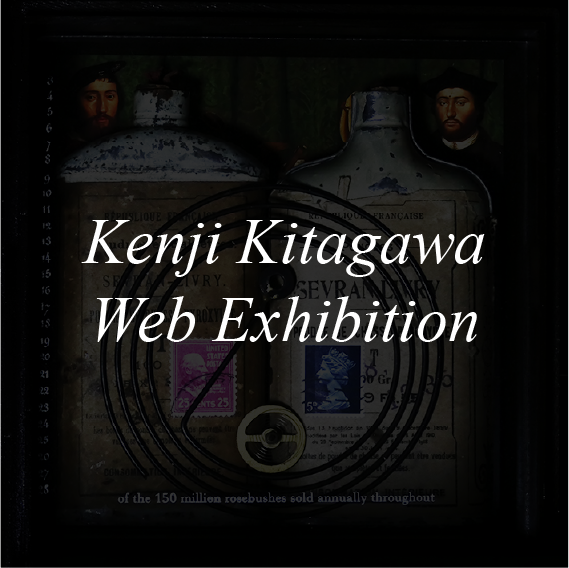サントリー美術館のO氏から招待券を頂いていたので、19日(日)まで開催中の『歌麿・写楽の仕掛人−−その名は蔦屋重三郎』を見に行った。版画は複数性なので出版の原理と重なるものがある。だから版画を商う画商には、出版プロデューサーとしてのセンスと、時代を読んで先駆的に勝負する胆力が要求される。しかし蔦重以前にも以後にもそのような人材はいなかった。ただ蔦重のみが18世紀後半の江戸に出現し、歌麿・写楽・山東京伝・大田南畝(なんぼ)といったスターを輩出させ江戸文化の最先端を創造した。その眼差しを現代に移せば、画商が文化の先端を変革したというような点では、南画廊の志水楠男氏がそれに相当するだろう。そしてその後の企画力の高さでは佐谷画廊の佐谷和彦氏が浮かび上がるが、佐谷氏が亡くなられた時点で、何かとてつもなく大事なものが終焉し、加速的に美術の分野は歪んだ、品の悪い方向に迷走し、それは今日に至っている。時代を作るのは具体的な「人」である。「ルネサンスはいつ終わったか!?」と尋ねて、即答出来る人が何人いるであろうか?ーー答えは1520年であり、それはラファエロが死んだ年である。(1519年にダ・ヴィンチが死去)。このあたりで、そろそろ現代の美の仕掛人が登場しなければ、美術は本当につまらない分野に落ちていくだろう。
サントリー美術館のO氏から招待券を頂いていたので、19日(日)まで開催中の『歌麿・写楽の仕掛人−−その名は蔦屋重三郎』を見に行った。版画は複数性なので出版の原理と重なるものがある。だから版画を商う画商には、出版プロデューサーとしてのセンスと、時代を読んで先駆的に勝負する胆力が要求される。しかし蔦重以前にも以後にもそのような人材はいなかった。ただ蔦重のみが18世紀後半の江戸に出現し、歌麿・写楽・山東京伝・大田南畝(なんぼ)といったスターを輩出させ江戸文化の最先端を創造した。その眼差しを現代に移せば、画商が文化の先端を変革したというような点では、南画廊の志水楠男氏がそれに相当するだろう。そしてその後の企画力の高さでは佐谷画廊の佐谷和彦氏が浮かび上がるが、佐谷氏が亡くなられた時点で、何かとてつもなく大事なものが終焉し、加速的に美術の分野は歪んだ、品の悪い方向に迷走し、それは今日に至っている。時代を作るのは具体的な「人」である。「ルネサンスはいつ終わったか!?」と尋ねて、即答出来る人が何人いるであろうか?ーー答えは1520年であり、それはラファエロが死んだ年である。(1519年にダ・ヴィンチが死去)。このあたりで、そろそろ現代の美の仕掛人が登場しなければ、美術は本当につまらない分野に落ちていくだろう。
以前に、このメッセージで、地方に住まわれている方々から私の作品を直接見たいし、コレクションもしたいのだが、近くで個展をされないのか!?という旨の手紙やメールを頂いている事を記した事があった。そして何か良い方策はないのかという問いかけをした事があった。その結果、最も多かった意見が、私のホームページで作品を買えるシステムを開設して欲しいという内容のものであった。確かに私の作品に関心があっても、遠方のために間近で見れず、ために入手出来ない方が未だ、どれだけいる事であろうか。しかし、オブジェやタブローの微妙な調子は直接見てもらわなければ伝わらないものが一方では確かにある。だが、例えば私の写真の作品ならば、それが可能かもしれない。しかし、それを実現する為には,ネットだけの限定コレクションの設定も必要となってくるであろう。作品は、それを必要とする人に所有される運命を持っていると思う。大変だが、開設に向けてここは前向きに考えてみたいと思う。