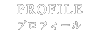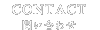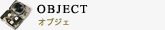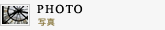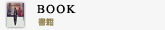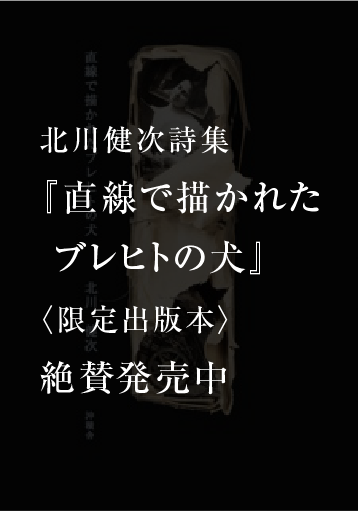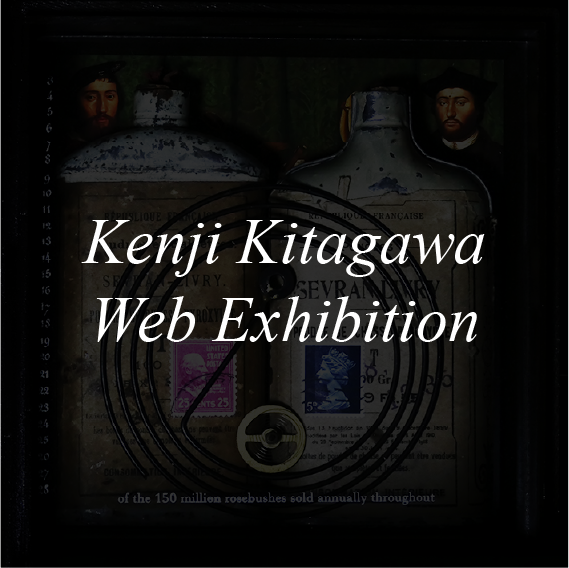9月初旬の10日間ばかり、撮影を兼ねてパリに滞在していた折りに、パリの画廊で友人の写真家が個展を開催するタイミングと重なったので、そのオ―プニングに行った事があった。その時にいろいろな人と話す機会があり気づいた事であるが、最近の写真の分野では、写真と併せてその作者のコンセプトなるものが重視されており、差別化されたそのコンセプトの独自性(?)なるものを持って販売アピ―ルの具としているという傾向がある事を知った。ちなみにその友人の写真家の作品は〈寡黙〉を持って十分に主張している作品なので、殊更な言葉を必要とするほど軟弱ではない強さがあったが、その会場で私は、パリの写真界に限らず、それがこの分野における現在の主たる傾向である事を痛感したのであった。……当然な事であるが、表現された作品は元来が〈匿名〉であり、そこに取って付けたような作者の言葉は必要ない筈である。優れた作品ならば、それ自体が十分に饒舌な筈である。……売らんかなの為に、この作者の世界観、この作者の視点の在所はこんなに独自的云々…………といったコンセプトなるものの販促めいたものがセットで必要とされているところに、この分野の今日の苦戦と立ち位置の覚束無さを私は覚えたのであった。この傾向の行き先は、つまりは、作者とその作品を細いものにしていき、観る事のアニマから随分と程遠いものにしていくに相違ない。
また別な傾向としては、50、60年代に写真家として盛りを過ごした人達がいるが、昨今の「あの熱かった時代を回顧して意味を照射する」という流れに乗って価値付けされているものの、つまりは表現者として現在形の活動、新たな表現領域の開拓といった活動からは遠い安穏の人達である事に、私は表現者の生き方として、些かの疑問符を持って見ているのであるが、先述した、いたずらなコンセプトを一切必要とせず、またこの国における写真集の金字塔ともいえる作品を60年代に早々と発表しながらも、その事に安住する事なく、自らの突き上げるデ―モンに煽られるようにして、果敢に次なる可能性に挑み続けている写真家(写真術師)が、この国に唯一人存在する。……川田喜久治氏である。
9・10月に日本橋高島屋で開催した私の個展に川田喜久治氏が来られた折りに、最近刊行されたという写真集の事を話されたのであるが、その写真集が先日、我がアトリエに送られて来た。……写真集のタイトルは『遠い場所の記憶: 1951 ―1966』。1951年、高校卒業の時に川田氏が撮った写真をカメラ雑誌のコンテストに応募して、たちまちその写真が特選となるが、その際の審査は木村伊兵衛と土門拳であったという話には、1つの真実が潜んでいる。……時代の常として、どの分野においても後に突出した人物となっていく逸材は、初めから或る種の完成度の高さと、潜んでいる胚種の多層さを持っているのであり、木村伊兵衛、土門拳といった強度な慧眼の持ち主は、そこに次代の新たな才能をたちまち見抜いた事は間違いない。……この写真集は川田氏の初期から1966年までに撮った数多の写真から厳選して構成されたアンソロジーであり、その存在感と、内容の濃密さからは、「オブジェとしての写真集」という形容が相応しい。
写真集の最初(序章)は、戦後の世相をひんやりと切り開く描写から始まっているが、次第に多層的な表現の放射へと拡がり、この世の内実が魔的なものに満ち充ちていることを、まるで千の暗い仏壇の闔を開いていくように、この写真集は次々と展開していく。そのいずれもが象徴性と多弁性を持って此方に挑みかかってくるのであるが、……わけても私の興味を引いたのは、「Mのトルソ」と題された、身に付いた筋肉を誇示している男の顔無しの写真であった。……顎から上の顔面が撮されていない〈三島由紀夫〉の腕組む胸部を写した何とも不穏なトルソであるが、後の自刃を暗示しているようでもあり、ある意味で、三島の魔的な肖像を欠落故により饒舌に表してもおり、私は禁裏を垣間見るような一種の戦慄を持って、この特異な写真に見入ったのであった。三島は若き日の細江英公を指名して写真集『薔薇刑』なる美の伽藍を築いたのであるが、川田氏のこの写真を前にすると、『薔薇刑』が装いの表象、いとも脆い表側の顔にさえ見えてくるのであるから、真に川田喜久治氏は恐ろしい。……私はこの写真集に接して漸く気づいたのであるが、光とは、闇を照らす陽的な存在ではなく、闇に蠢く万象の不気味なる実相を覆い隠す為の嘘のフィルタ―のごとき存在として在るのだと思い知らされたのであった。以前に私は川田喜久治氏を評して、ゴヤの魔的なる遺伝子を継ぐ正統と断じた事があるが、私は更に上田秋成の名前を借りて、この写真集を現代版『雨月物語』とでも言い表したい衝動に駆られているのである。


川田喜久治写真集『遠い場所の記憶: 1951 ―1966』に関するお問い合わせは、PGIにて受け付けております。―是非のご高覧をお薦めしたい、写真による暗黒奇譚を紡いだアンソロジー、後世に間違いなく残る、オブジェとしての写真集です。