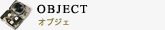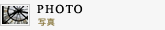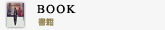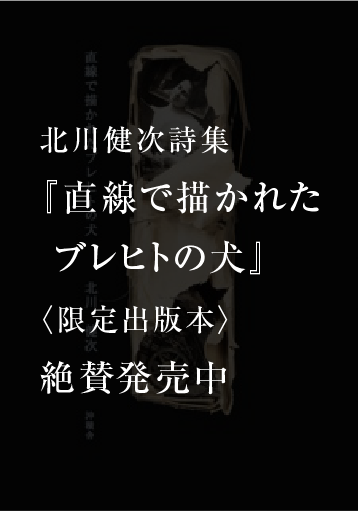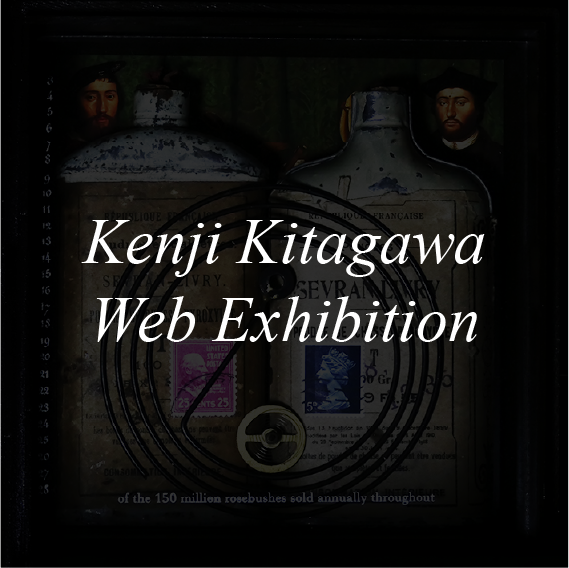敗戦記念日の8月15日になると、毎年その頃に大戦時の悲惨な映像が流れ、幾つかの特集番組がテレビで流される。先日たまたま観たNHKの朝の番組もその1つであった。(観られた方はかなり多いと思われる)……先ず映し出されたのは、レイテ戦で日本兵が突撃し、銃火や火炎放射器で焼かれて次々と戦死していく映像であった。
……次に作家・大岡昇平の『レイテ戦記』の一節が朗読で流された。……それは、ある上官の事を書いた文章であるが、その上官の事を実に卑怯な男で、部下からの信頼もなく、いかに惨めな姿で死んでいったかを、その上官の実名を挙げて書いたものであった。……(ちなみに、この『レイテ戦記』は詳細な資料調査に基づいたものと評価され、反戦文学の代表作と評されている)。当然多くの読者は、実名で書かれたこの上官の事を事実とし、卑怯で惨めな男と記憶してしまう。……しかし大岡昇平の『レイテ戦記』が発表(1967年から連載開始)されていらい、この事で、実に50年以上もの間、屈辱に耐えて来た人達がいた。大岡に卑怯な男と実名で書かれた上官の遺族の人達である。
……番組では、当時5歳くらいであった上官のお嬢さん(現在は90歳くらい)が登場し、「記憶の中の父は絶対にそのような卑怯な人ではなかった。戦地での父の真実の姿を知りたい」と話す映像が映し出された。…………しかし番組製作時に、お嬢さんの長年の無念を晴らす奇跡が起きる。……お嬢さんは、偶然或る番組でレイテ戦の生存者(現在100歳くらい)が未だ生きている事を知り、テレビ局のスタッフとその人の住居へと赴いた。……「ひょっとして、その方は父と接点があった方かもしれない」……藁をもすがる想いで、その人と面会した。(画面に映るその人は100歳に達しているとは言え、矍鑠としていて、記憶の冴えがしっかりとした人であった)。
……レイテ島には当時84000人の兵隊がおり(その内80000人が戦死)、配属された部隊の数もたくさん在り、両者に接点がある方が難しい。……しかし驚いた事に、その人と上官は同じ部隊であり、上官の人となりは未だしっかりと記憶に焼き付いているという。そして画面は、上官とその人、そして部隊の全員が写っている集合写真のアップとなった。(写真から、上官の温厚さの中に秘めた信念の芯の強さが伝わって来る)。……その人は語り始めた。……「上官は実に立派な方で部隊の部下からも慕われていました」「私が生きて帰れたのも上官のおかげです。上官は(私はここで死ぬが、お前は生きろ!生きて日本に帰れ!!)そう言って亡くなられました。この本の中に書かれているような卑怯な人ではありません」と、はっきりと断言したのであった。
……私はここに2つの奇跡を観て感動した。1つは、この生存者にまるで導きのように上官の遺族が存命中にギリギリで会えた事、もう1つは、上官がこの一兵卒の部下を日本に帰した事で、80年後に自分の汚名を晴らす事が出来、お嬢さんに、自分の戦地での実像を伝えられようとは想像していなかったに違いない、何という運命の、しかし不思議な糸の結び付きかと、私は感動したのであった。
……「これで長年の辛かった思いが晴れました。有難うございました」とそのお嬢さんは語ったが、最後に「死人に口はありませんからね」とも静かに語った。……それは大岡昇平に、「卑怯者で惨めな姿で死んでいった」と書かれた事に、既に死者となってしまった父は何も言い返せない事への無念を語る言葉であり、悔しさであった。この遺族の方の秘めた本心には、明らかにされたこの部下の証言を大岡に見せて、何故あのような根拠のない、悪意とも取れる文章を書いたのかを抗議文か何かをしたためるか、或いは直接会って問う事にあった事は想像に難くない。……しかし大岡は35年前の1988年に亡くなっており、この無念はもはや届かない。
 ……しかしここに、大岡昇平が未だ存命中に、手紙で強烈な抗議文を書いて大岡に送った当時26才の若僧がいた。……誰あろう、私である。
……しかしここに、大岡昇平が未だ存命中に、手紙で強烈な抗議文を書いて大岡に送った当時26才の若僧がいた。……誰あろう、私である。
……昔、角川書店から電話が入り、大岡昇平の『中原中也』を文庫で出すので、その挿画を表紙に描いて欲しいという依頼があった。私はその本の事は知っていた。先達の、銅版画の詩人と言われた駒井哲郎さんの版画『笑う赤ん坊』を大岡の『中原中也』の単行本の表紙にしたのを覚えていたのである。中原中也の無垢さの内の御しがたい突き上げを、この版画の選択は実にピタリと合っており、表紙の挿画として突出した素晴らしい出来だと記憶していた。だから、その駒井さんと勝負しようと思い、編集者との打ち合わせを楽しみにしていたのであった。
 ……後日担当の編集者に会うと、浮かぬ顔で「実は大岡先生が、文庫の時にはこの写真を使って欲しいと言って、これを指定してきたのです」と言う。……それは中原中也が確か就職活動の必要を覚えて撮った書類に貼る為の写真で、よく知られたあの写真と違い凡庸な面相で写っている。
……後日担当の編集者に会うと、浮かぬ顔で「実は大岡先生が、文庫の時にはこの写真を使って欲しいと言って、これを指定してきたのです」と言う。……それは中原中也が確か就職活動の必要を覚えて撮った書類に貼る為の写真で、よく知られたあの写真と違い凡庸な面相で写っている。
 ……私は「人は表紙のセンスの妙で購買を決める場合が多いので、これじゃ売れませんよ」と言った。そして「既存の写真をただ印刷するだけなら、何もあえて私がやる必要はないでしょ」とも言った。実はこの配慮は大岡自身の為でもある。どれだけ売れるか、内実、印税は大岡に限らずどの作家にとっても生命線なのである。これではすぐに絶版は必至と見た。話してみると、……編集者も本音は、この中原ではなく、あの写真を使いたいらしい。
……私は「人は表紙のセンスの妙で購買を決める場合が多いので、これじゃ売れませんよ」と言った。そして「既存の写真をただ印刷するだけなら、何もあえて私がやる必要はないでしょ」とも言った。実はこの配慮は大岡自身の為でもある。どれだけ売れるか、内実、印税は大岡に限らずどの作家にとっても生命線なのである。これではすぐに絶版は必至と見た。話してみると、……編集者も本音は、この中原ではなく、あの写真を使いたいらしい。
まぁしかし私も生活がある。……その頃に芥川賞をとった池田満寿夫さんが、当時20代の私が画廊契約でも大変なのを心配してくれて、角川書店での挿画の仕事を前から私に紹介してくれていたのであった。だから、まぁやるしかない。

……とまれ大岡昇平の指定した写真を採用せず、私は、あのよく知られた写真を製版屋にまわして写真製版で作らせ、濃いセピアのインクを刷ってレイアウトをし、編集者に渡して文庫本が出来上がった(画像掲載)。……この仕事において、当然、私の中原中也への私的解釈など何も入らず、既存のままの昔からの中原中也の顔がそこに刷りあがっていた。
………それから半年くらい経った頃であったか。雑誌の『太陽』の中原中也特集号が出た。本屋で立ち読みをしていると末尾辺りに、大岡昇平の『中原中也像の変遷』と題する一文が載っていた。中也像の変遷?とは何だ?意味がピンと来ないまま、一読して私は大岡昇平に失望した。そして、大岡、呆けたか!!?とも思った。
その文章は実に馬鹿げた論旨で、一言で言えば、私(大岡)が身近にいてよく知っている中原中也の実像と違い、中原を知らぬ次々の世代の読者は、彼のイメ―ジを女性的な弱い像として捕らえている傾向がある。具体的な例を挙げれば、以前に私の『中原中也』の表紙画を担当した北川健次がそれである。実像を知らない甘いイメ―ジで中原中也像を作り上げた北川はまがい物である!と断じているのであった。
……先述した通り、私はこの中原中也の写真を全く私的解釈などで変化せず、角川の編集者に用意してもらった写真をそのまま製版屋に回し、編集者がせめてセピアの古色でと言うので、そのまま刷っただけの、昔と何ら変わらない中原中也のままである。……自分の言う事を無視した若僧と私の事が映ったのか、とにかく久しぶりに来た原稿依頼で高ぶったのか、あろう事か、昨今の誰も抱いていない女性的な中原中也のイメ―ジに変化した幻をそこに見て、私が作った表紙に、大岡は怒りのままに長いまつ毛を生えさせてしまったらしい。
……私は、この文章を書くに至った大岡の内面を透かし見た。……誰もが平伏する私に対し、この北川という生意気な若僧は……という想いと同時に、中原中也をよく知っているのは身近にいた私だけであるという念が日増しに増して来ており、それをこの駄文に込めたのであろう、そう思った。しかし、まがい物と活字でしっかりと書かれた事は、さすがに許しがたいものがある。呆けた相手とは言え、売られた喧嘩は、矜持として買うのが私の流儀である。さっそく私は抗議文を書く事にした。編集者から大岡の住所を訊き、便箋5枚ばかり書いて、「くらえ!!」とばかりに投函した。
「貴殿が小心者でないならば、また自分の書いた文章にプロの作家として自責を負う自覚があるならば、この手紙を途中で破る事なく最後まで読まれたし。この手紙文は先日書いた中原中也に関する貴殿の明らかな間違いを理路整然と正す文章である。…………」から始まる文は、最後に「私は中原中也の詩や文章の熱心な読者の一人であるが、その彼の文章の中に貴殿について書かれた文章は、小林秀雄と違い僅かしか無い事もまた事実です。最後になりますが、貴殿の小説について何か書く事は礼儀かもしれません。しかし、多くの読者がそうであるように、私は三島由紀夫や松本清張の熱心な読者であり、彼らの作品や生き方から多大な影響を受けています。しかし、多くの人達がそうであるように、貴殿の小説は全く読んでいないので、何も書く事はありません。……定家卿曰く、芸道の極意は身養生に極まれりと。御身お大事に。北川健次」………………今、記憶の限りに書いているが、まぁこんな内容であった。
…………しばらくして、反応があったが、それは私の予期した通りの事であった。私でなく角川の編集者に怒りの矛先が行き、以来、私の挿画の仕事は無くなった。しかし良くしたものでその後に他の出版社から挿画の依頼が来た。またまがい物と書かれた雑誌『太陽』ともその後で何故か縁があり、エッセイを書いたり、また編集長から企画の相談を依頼されるようになるから、人生はわからない。
……さて、抗議文の中で松本清張の名前が出て来たが、これには理由がある。……大岡昇平は松本清張の文学を否定し、「彼の作品は純文学でないから認めない」と発言しているのであるが、彼はいつから純文学の裁き手になったのであろうか?……文壇では小林秀雄を我が身の借景としている事から来る、この増長とも取れる発言は、如何にも不可解であり、如何にも小さい。
……松本清張は『或る小倉日記伝』で芥川賞を授賞した後、周知の通り、社会派推理小説という新分野を切り開き、その分野の越境の様は拡がりを見せながらとどまる事を知らない生涯であった。純文学などという狭い意識にこだわっていては果たせないスケ―ルの幅であり、私は20代から大きな影響を受けている。……「純文学ではないから認めない」という大岡の発言を嫉妬だと断ずる人もいるが、底辺から這い上がって、一気に小説家の水準を超える作家へと上がっていった松本清張への蔑視もあるように思われる。『神聖喜劇』などの著作で知られる小説家の大西巨人氏は、大岡の発言の中に矛盾や屈折を早々と看破しているが、やはりと思わせるものがある。
……最後に、『レイテ戦記』に戻るが、詳細な調査として評価された面があるこの作品。実は正確な戦史でなく、実質は小説であるが、この点にそもそもの構造的な無理がある。戦史で言うなら、吉田満氏の『戦艦大和ノ最期』の方が遥かに正確さと密度において優れており、吉村昭氏の『関東大震災』の方がその詳細な調査の深さにおいて群を抜いている。この度の番組で明らかになった『レイテ戦記』の虚実のほころび。……今、もし大岡昇平の研究家なる者が存在するとしたならば、このレイテ戦記の虚の部分を徹底調査して洗い直す必要があると、私は汚名を受けた遺族の方々に代わって考えるのである。
……今回のブログはマチスについて書く予定でいたが、思いがけずテレビ番組で、著者の無責任さを知ってしまい、このブログを書く事になってしまった。……さぁ次は何を書こうか、ともかくご期待頂けると有り難いです。
 1つは銀座ヒロ画廊で開催されている『浜田知明展・戦争の影/人間愛』である。浜田さんとも、お付き合いは長かった。…私の人生で関わった版画家はごく少数に限られており、先達の棟方志功さん、駒井哲郎さん、池田満寿夫さん、加納光於さん、そして浜田知明さんだけであり、いずれも日本の版画史に間違いなく残っていく人達である。
1つは銀座ヒロ画廊で開催されている『浜田知明展・戦争の影/人間愛』である。浜田さんとも、お付き合いは長かった。…私の人生で関わった版画家はごく少数に限られており、先達の棟方志功さん、駒井哲郎さん、池田満寿夫さん、加納光於さん、そして浜田知明さんだけであり、いずれも日本の版画史に間違いなく残っていく人達である。 ……もう1つは谷中の朝倉彫塑館で開催されていた『生誕100年ASAKURA Kyoko』展である。…朝倉響子さんは日本の彫刻界を牽引した朝倉文夫の次女で、姉は舞台美術家の朝倉摂さん。
……もう1つは谷中の朝倉彫塑館で開催されていた『生誕100年ASAKURA Kyoko』展である。…朝倉響子さんは日本の彫刻界を牽引した朝倉文夫の次女で、姉は舞台美術家の朝倉摂さん。
 …当日は彼の代表作の一つである『櫻の園』が上映される。成田氏の企画によるこの映画は、1990年の「キネマ旬報」ベストテンの第一位になり、その年の賞を総なめにして、現代日本映画の名作として今も評価が高い。
…当日は彼の代表作の一つである『櫻の園』が上映される。成田氏の企画によるこの映画は、1990年の「キネマ旬報」ベストテンの第一位になり、その年の賞を総なめにして、現代日本映画の名作として今も評価が高い。

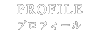
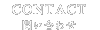
 …………学生時代、店主に嫌な事を言われながらも、三茶書房はしかしめげずに度々行っていた。そのガラスケ―スの中に、今度は
…………学生時代、店主に嫌な事を言われながらも、三茶書房はしかしめげずに度々行っていた。そのガラスケ―スの中に、今度は その際にその展示の場所で、30年以上欲しくて探し続けていた
その際にその展示の場所で、30年以上欲しくて探し続けていた ……しかし、その奥に入って私は我が目を疑った。……あの学生時代以来、ずっと意識し続けていた江戸川乱歩の件の書「うつし世はゆめ……」が奥の方で泉鏡花、谷崎潤一郎の書と並んで静かに展示されていたのであった。
……しかし、その奥に入って私は我が目を疑った。……あの学生時代以来、ずっと意識し続けていた江戸川乱歩の件の書「うつし世はゆめ……」が奥の方で泉鏡花、谷崎潤一郎の書と並んで静かに展示されていたのであった。
 ……しかしここに、大岡昇平が未だ存命中に、手紙で強烈な抗議文を書いて大岡に送った当時26才の若僧がいた。……誰あろう、私である。
……しかしここに、大岡昇平が未だ存命中に、手紙で強烈な抗議文を書いて大岡に送った当時26才の若僧がいた。……誰あろう、私である。 ……後日担当の編集者に会うと、浮かぬ顔で「実は大岡先生が、文庫の時にはこの写真を使って欲しいと言って、これを指定してきたのです」と言う。……それは中原中也が確か就職活動の必要を覚えて撮った書類に貼る為の写真で、よく知られたあの写真と違い凡庸な面相で写っている。
……後日担当の編集者に会うと、浮かぬ顔で「実は大岡先生が、文庫の時にはこの写真を使って欲しいと言って、これを指定してきたのです」と言う。……それは中原中也が確か就職活動の必要を覚えて撮った書類に貼る為の写真で、よく知られたあの写真と違い凡庸な面相で写っている。 ……私は「人は表紙のセンスの妙で購買を決める場合が多いので、これじゃ売れませんよ」と言った。そして「既存の写真をただ印刷するだけなら、何もあえて私がやる必要はないでしょ」とも言った。実はこの配慮は大岡自身の為でもある。どれだけ売れるか、内実、印税は大岡に限らずどの作家にとっても生命線なのである。これではすぐに絶版は必至と見た。話してみると、……編集者も本音は、この中原ではなく、あの写真を使いたいらしい。
……私は「人は表紙のセンスの妙で購買を決める場合が多いので、これじゃ売れませんよ」と言った。そして「既存の写真をただ印刷するだけなら、何もあえて私がやる必要はないでしょ」とも言った。実はこの配慮は大岡自身の為でもある。どれだけ売れるか、内実、印税は大岡に限らずどの作家にとっても生命線なのである。これではすぐに絶版は必至と見た。話してみると、……編集者も本音は、この中原ではなく、あの写真を使いたいらしい。














 ……いよいよ明後日から9月である。しかしまだ暑い、暑すぎる。あまりの暑さで蝉も鳴かない。……さて、その明後日の9月1日と云えば、大正12年に起きた関東大震災があった日である。最近読んだ
……いよいよ明後日から9月である。しかしまだ暑い、暑すぎる。あまりの暑さで蝉も鳴かない。……さて、その明後日の9月1日と云えば、大正12年に起きた関東大震災があった日である。最近読んだ


















 東京の日本橋にある
東京の日本橋にある 普通に開催されている展覧会というものは、作家が作った新作を並べる事に終始しているが、今回の展覧会にはその核に秘めた強い骨子がある。ー それは、現代の衰弱を極めた版画界への鋭い切っ先が、問題提示として在るという事である。私のアトリエには毎日展覧会の案内状が送られてくる。そのほとんどが芸術とは無縁と化したイラストレーションのごとき内容であるが、その中でも悲惨を極めているのが〈版画〉である。強いアニマ、馥郁としたポエジー、つまりは見る事の愉楽からはほど遠い、ペラペラと化した状況へと陥っているのである。原因はある程度わかっている。技術(それも既存の)しか教えられない美大の形骸化した指導のやり方。唯のマニアしか読者として意識しない版画誌の編集スタイル。
普通に開催されている展覧会というものは、作家が作った新作を並べる事に終始しているが、今回の展覧会にはその核に秘めた強い骨子がある。ー それは、現代の衰弱を極めた版画界への鋭い切っ先が、問題提示として在るという事である。私のアトリエには毎日展覧会の案内状が送られてくる。そのほとんどが芸術とは無縁と化したイラストレーションのごとき内容であるが、その中でも悲惨を極めているのが〈版画〉である。強いアニマ、馥郁としたポエジー、つまりは見る事の愉楽からはほど遠い、ペラペラと化した状況へと陥っているのである。原因はある程度わかっている。技術(それも既存の)しか教えられない美大の形骸化した指導のやり方。唯のマニアしか読者として意識しない版画誌の編集スタイル。